「なんとなく」で契約してしまうと、あとから大きな損失やトラブルにつながる——それが店舗の賃貸借契約です。今回は、実際に多数の店舗契約をサポートしてきた「くっつー」と「やまや」が、店舗契約で気をつけるべき“3つの重要ポイント”について、リアルな事例を交えながら解説します。
一見すると難しそうな賃貸借契約の話も、わかりやすく具体的に話しているので、これから店舗を借りたい方はもちろん、すでに店舗を運営している方にもきっと役立つ内容になっています。契約トラブルを未然に防ぎ、安心して事業をスタート・継続させたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
店舗契約の注意点①「業種制限は明確に」
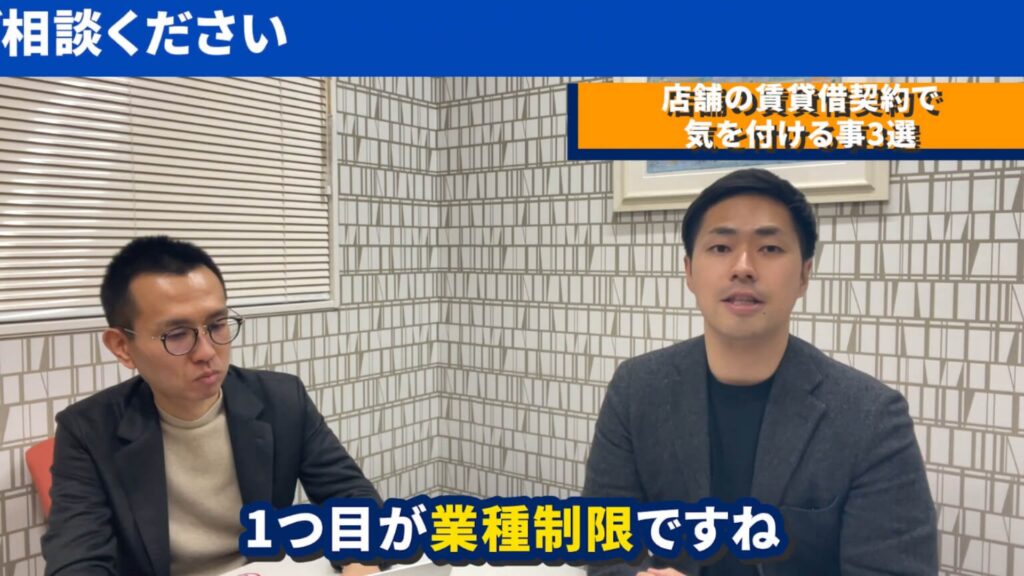
店舗の契約では「業種」の取り決めが非常に重要です。住宅契約とは違い、何を目的として使うかによってトラブルのリスクが大きく変わってきます。実際のトラブル事例をもとに、業種を具体的に記載することの重要性をお話しします。
業種を曖昧に書くとどうなる?よくあるトラブル事例
くっつー:住宅と違って店舗の契約って、やっぱり事業目的ですので注意点が多いんですよね。
やまや:確かに、住宅契約とは勝手が違う感じがしますよね。具体的にはどんな点が大事なんですか?
くっつー:まず1つ目は「業種制限」です。これは本当に重要で、契約書にどう書くかでトラブルを防げるかが決まります。
やまや:業種って、ラーメン屋とか美容室とかそういうのですよね?
くっつー:そうです。でも契約書に「店舗及び事務所として使用」みたいにざっくり書いてしまうオーナーさんも多くて、それがトラブルのもとになるんです。
やまや:え、それだと何をやってもいいってことになっちゃいません?
くっつー:そうなんです。だから「ラーメン屋」など、できるだけ具体的に書いておくのがおすすめです。
やまや:業種を具体的に書いておけば、トラブルを未然に防げるってことですね。
くっつー:そうです。あと業種を変えたい場合は、事前にオーナーの承諾を得るように契約書に明記しておくと安心です。

店舗契約では、用途欄に「飲食店」「物販」などとしか書かれていないケースが多く見受けられますが、これは非常にリスクが高い内容です。ビル内で同業種が複数存在すると、集客や騒音、臭いなどをめぐるトラブルに発展する可能性があります
業種を絞るべき理由と契約書での明記のポイント
やまや:でも業種を具体的に書くと、逆に借り手側がやりにくくなるってことはないんですか?
くっつー:そこはバランスですね。確かに「飲食店」でざっくり書けば、あとで事業展開しやすいっていう考えもあります。でもオーナーからしたら、それが焼肉屋とか居酒屋とかに変わったら困るわけです。
やまや:確かに。同じビルに同業種が増えたら、集客とか匂いの問題とか出てきそうですし。
くっつー:そうです。実際にあった話なんですけど、最初は焼き鳥屋で契約していたのに、うまくいかなくて焼肉屋に変えた。そしたらビル内の既存の焼肉屋さんからクレームが来たんですよ。
やまや:あー、それは揉めますね。しかも契約書には「飲食店」って書いてあっただけなら、借り手側は問題ないと思ってますよね。
くっつー:そうなんです。だから最初の契約で「この業態でやる」ってはっきり書いておいて、もし変更したいなら「オーナーの書面承諾を必要とする」って条項を入れておくといいです。
やまや:なるほど。万が一、事業の方向性が変わる場合でも柔軟に対応しつつ、借り手・貸し手の双方にとって大切な“信頼関係”も壊さないようにするってことですね。
くっつー:そうです。業種制限をきちんと設定しておくことで、トラブルが起きたときにも契約書を元に話を進められるので安心です。

契約時に業種を絞ることで、ほかのテナントとのバッティングやオーナーとの認識ズレを防ぐことができます。特にビル内に複数テナントが入る場合、業種かぶりは重大な問題につながります。業種の変更が生じた際の条件をあらかじめ契約書に明記しておけば、後々の交渉もスムーズです
店舗契約の注意点②「中途解約条項のチェックは必須」

住宅の契約と違って、店舗の賃貸借契約では「中途解約」のリスクが非常に重要なテーマになります。特に長期契約や定期借家契約の場合、思わぬタイミングで解約したくなったときに備えておくことが必要です。
ここでは、中途解約に関する具体的なトラブルや、借主・貸主それぞれの視点から見た注意点を紹介します。
住宅契約とは違う!店舗契約での中途解約リスク
やまや:次のポイントは「中途解約条項」ですね。これも住宅と店舗じゃ大きく違いますよね。
くっつー:そうなんです。住宅だとだいたい2年契約で、更新していく形が一般的ですけど、店舗は定期借家で5年とか10年とか、長期間で契約することが多いんです。
やまや:たしかに。しかも事業だから、赤字が続くと早めに撤退したくなるときもありますよね。
くっつー:そうなんですよ。撤退せざるを得ない状況って、実はよくあるんです。だからこそ、契約書に「中途解約できる条件」をしっかり書いておかないと、借主にとっても貸主にとっても大きなリスクになります。
やまや:借りる側からしたら、やめられないって相当きついですよね。
くっつー:はい。実際、店舗契約で一番重要なのがこの中途解約条項かもしれません。例えば「契約開始から3年は解約不可。その後は6か月前の通告で解約可」みたいに設定するケースが多いです。
やまや:それでもまだキツイって感じる借主さんもいるかもしれませんね。
くっつー:だから私の場合「最悪でも6か月前通告で解約可、ただし敷金は全額没収」っていう条項を入れることが多いです。
やまや:なるほど、それなら借りる側も納得しやすいですね。

店舗契約における中途解約条項は、住宅とは異なり経営状況に応じた「撤退の柔軟性」を持たせる必要があります。長期契約の途中で事業撤退せざるを得ない場合、解約条件が曖昧だと法的なトラブルに発展することもあります。6か月前通告や敷金償却など、具体的な解約条件をあらかじめ定めておくことで、借主・貸主双方のリスクを減らすことができます
実際に使える中途解約の契約例とオーナー・借主双方の視点
やまや:でもオーナー側からすると、いつ撤退されるかわからないのって不安じゃないですか?
くっつー:もちろんです。だからこそ「撤退する場合は6か月前までに通知」「退去時の条件を明確に」っていう形で、オーナー側のリスクも軽減するようにしています。
やまや:なるほど、しっかり準備できるようにしているんですね。
くっつー:そうです。あと「次のテナントを連れてきたら違約金なしでOK」っていう“代替借主条項”も有効です。これなら借主は安心して撤退できるし、オーナーも次の入居者がすぐ決まれば損しません。
やまや:借主が後継テナントを探すって、実はオーナーにとってはすごくありがたい話ですよね。
くっつー:はい、信頼関係があればそれも可能ですし、不動産会社がそこをサポートする形も多いです。専門知識を持った店舗系の仲介業者と組むことも、リスク軽減につながります。
やまや:なるほど、契約時点でどこまで現実を見据えておくかっていうのが大事なんですね。

「中途解約」のルール設定には、実務的な視点と現実的な柔軟性の両立が求められます。事業撤退のリスクは飲食・小売業などにおいて常につきまとうものであり、撤退条件をあいまいにしてしまうと法的な争いや金銭トラブルを招くこともあります。「6か月前通告+敷金没収」「代替借主を連れてきた場合は違約金免除」といった条項は、実務上でも効果的であり、双方にとって納得しやすい内容となります
店舗契約の注意点③「維持管理区分を細かく決める」

店舗運営において「設備のトラブル」は避けられません。その際に問題となるのが「どこまでを貸主が直すのか」「どこからが借主の責任なのか」という維持管理の区分です。
これが曖昧だと、トラブルが起きたときに責任のなすり合いになり、関係が悪化しかねません。ここでは、維持管理の責任区分を明確にする方法や、実際の事例を紹介します。
よく揉めるポイントとその対処方法
やまや:最後は「維持管理の区分」ですね。これはけっこう揉めるイメージありますね。
くっつー:本当にそうです。空調とか自動ドアとか、水道管とか、壊れたときに「どっちが直すの?」ってなることが多いです。
やまや:契約書に書いてあるんですか?
くっつー:はい。私たちは「資産区分表」っていう一覧表をつけていて、設備ごとにどっちの負担かを明確にしています。
やまや:へー、それはわかりやすいですね。全部言葉だけで書いてあったら、曖昧になりそう。
くっつー:そうなんです。契約書に一文だけで「引き渡し時の状態を維持してください」とかって書かれているだけだと、解釈がぶれるんですよね。
やまや:たしかに。たとえば空調が壊れたとき「これは引き渡し時に壊れていた」とか「借りたあとに壊したでしょ」とか、揉めますね。
くっつー:そうです。それを避けるために「点検は誰がする」「修理はどちらが負担」っていうのを具体的に分けておくといいです。
やまや:細かく決めておくと、後々スムーズなんですね。
くっつー:そう。特に水道や電気の一次・二次の分岐部分、空調の点検と交換、自動ドアの修理など、よくトラブルになる部分はしっかり書いておくべきです。

維持管理区分の明確化は、店舗契約において非常に重要なポイントです。トラブルが発生した際に責任の所在が曖昧だと、修繕費用の負担や対応スピードに差が出ます。「空調の点検は借主、交換は貸主」「一次側はオーナー、二次側はテナント」など、設備ごとにルールを決めておくことで、契約後も良好な関係を保つことができます
区分表の具体例と導入するメリット
やまや:その資産区分表って、実際にはどんなふうに作っているんですか?
くっつー:設備ごとに「点検」「修繕」「交換」を、それぞれ貸主・借主どちらがやるかを分けて表にします。たとえば空調なら「点検は借主」「交換は貸主」みたいに具体的に書いてます。
やまや:それめちゃくちゃわかりやすいですね。何が起きても、表を見れば判断できるってことですよね。
くっつー:そうです。たとえば自動ドアが壊れたら「これは借主の負担ですか?」って聞かれても、表を見ればすぐに「これは貸主側です」って言える。
やまや:それがないと、いちいち契約書を読み返して、曖昧な文言をどう解釈するかっていう話になりますもんね。
くっつー:実際に、他社が作った契約書でトラブルになった事例があって。空調が引き渡し後すぐに壊れたんですけど、契約書に詳細な区分がなかったから揉めたんです。
やまや:なるほど、それで結局どうなったんですか?
くっつー:契約の末尾にあった簡易的な条文を根拠に「借主が修繕すべき」と判断されました。でもそれ、借主からすると納得できないですよね。
やまや:それなら最初から表で明確にしておいたほうが、双方にとって安心ですね。
くっつー:本当にそうです。私たちのクライアントからも「区分表があってよかった」って感謝されることが多いです。

資産区分表とは、店舗に備え付けられた各設備について、点検・修理・交換などの責任範囲を明確に記した一覧表です。これがあるだけで、故障時の対応が迅速かつスムーズになり、無用なトラブルを避けられます。テンプレートを元に、契約ごとにカスタマイズする形で導入されるケースが多く、店舗契約には非常に有効な手段です
まとめ:トラブルを未然に防ぐ店舗契約のポイントとは
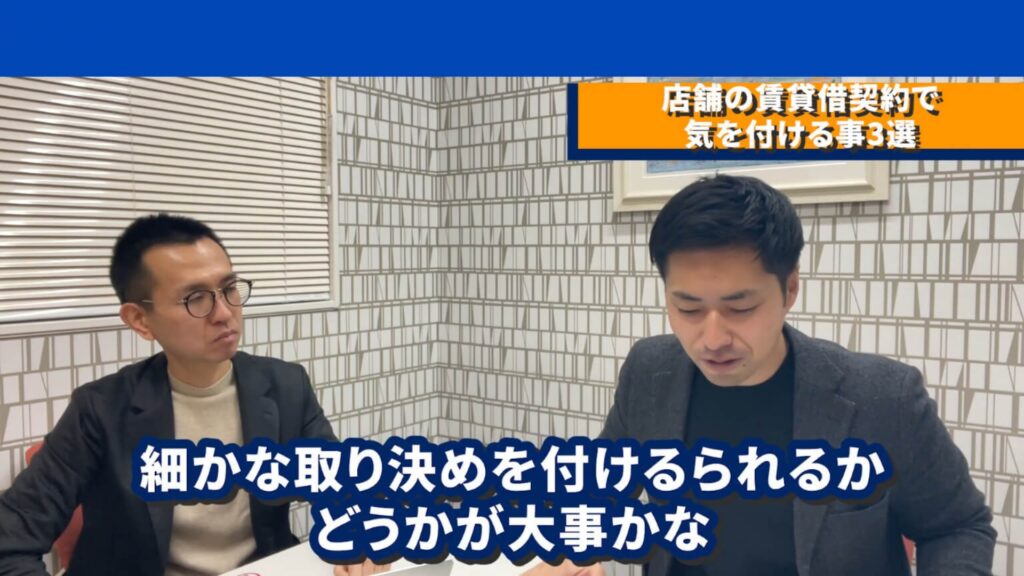
ここまで、店舗の賃貸借契約で特に注意すべき3つのポイントについてお話ししてきました。業種の制限、中途解約のルール、そして維持管理の区分。どれも契約前にしっかり取り決めておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
やまや:くっつーさん、今日もありがとうございました!やっぱり契約って「なんとなく」で進めちゃダメですね。
くっつー:そうなんです。特に店舗は事業の基盤になるので、最初の契約がすごく大事なんです。ちゃんと知識を持って望むだけで、無駄な揉め事はほとんど防げますから。
やまや:今回の内容、すごく勉強になりました。これから店舗を借りようとしている方、すでに借りている方にもぜひ見てもらいたいですね。
くっつー:そうですね。私たちは「テナントの窓口」として、店舗を貸したいオーナーさんや、借りたい事業者さんに向けて、こうした実務的な情報をどんどん発信しています。
やまや:店舗の契約や管理で「ちょっと不安だな」「誰かに相談したいな」ということがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。

店舗契約は、事業の土台となる重要なスタート地点です。トラブルを防ぐためには、契約書の内容をしっかりと把握し、必要に応じて専門家や不動産業者に相談することが不可欠です。今回紹介した3つのポイントは、すべて再現性が高く、今後の物件選びや交渉に直結する知識です
この記事から学べる5つのポイント

1. 業種は「できるだけ具体的」に契約書へ明記する
契約書に「店舗」や「飲食店」といった抽象的な記載だけでは、ほかのテナントとの業種バッティングが起きる可能性があります。「ラーメン屋」など業態を具体的に書くことで、後のトラブルを未然に防げます。
2. 業種変更には「オーナーの承諾が必要」と記載しておく
将来的に業態を変えたくなる可能性がある場合でも、事前にオーナーの承諾を得る旨を契約書に盛り込んでおけば、無用な揉め事を避けられます。事業展開の自由度と信頼関係の両立が可能になります。
3. 中途解約条項は「撤退前提」で現実的に設計する
事業がうまくいかない可能性も考慮し「6か月前通告+敷金償却」などの柔軟な中途解約条件を設定しておくと安心です。借主・貸主双方にとって納得のいく撤退条件を最初から合意しておきましょう。
4. 後継テナント条項を活用し「円満な撤退」を設計する
借主が後継テナントを見つけてくれば違約金不要で解約できる——こうした条項を入れておくことで、撤退時のストレスが軽減され、オーナーにとっても空室リスクを下げられる実用的な選択肢になります。
5. 設備管理は「資産区分表」で明文化して明確に分担する
空調・水道・自動ドアなどの修繕や管理責任を表形式で区分し、契約書に添付することで、故障時の責任のなすり合いを防止できます。特にトラブルの多い設備は細かく取り決めておくことが必須です。
