こんにちは、テナントの窓口のくっつーとやまやです。店舗物件をこれから運用するオーナーさんにとって「管理会社って必要?」「自分でできる?」という悩みはけっこう深刻ですよね。
本記事では、実際に店舗物件を多数手がけている私たちが、あなたにぴったりの管理スタイルを見極めるヒントを、リアルな会話形式でお届けします。
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
自主管理にはコスト面でのメリットがありますが、トラブルや規模が大きくなると手が回らないことも。一方で、管理会社に任せることで安心感は得られますが、費用面の負担が増すのも事実です。この記事を読み進めることで、あなたに最適な管理手法が見えてくるはず。まずは一歩目として「店舗物件オーナーの悩み」から整理していきましょう。
店舗物件オーナーの悩み「管理会社は必要?」

テナントが入る店舗物件では、住居用物件とは異なる管理の実態があります。まずは自主管理の可能性について見ていきましょう。
自主管理で十分?店舗物件における管理の特徴とは
くっつー:今日は「店舗物件の管理会社って必要ですか?」って質問について、やまやさんに聞いてみたいと思います。
やまや:はい!これ、オーナーさんからもよく聞かれますけど、結論から言うと、小規模な店舗なら管理会社は「いらない」ことが多いです。
くっつー:え、そうなんですか?住宅だと管理会社が当たり前じゃないですか?
やまや:そうなんですよね。でも住宅と違って、店舗って基本的に「自主管理」で十分なんですよ。というのも、例えば住宅なら、入居者が20人、30人っているから、家賃の回収や水回りのトラブル対応とか、大家さんひとりじゃ大変じゃないですか。
くっつー:確かに!「Aさんだけ家賃払ってない」みたいなことも起きますよね。
やまや:そうそう。店舗の場合は、入っているのが1社とかせいぜい数社なんで、基本的にトラブルが起きたらテナント側が自分で対応するんですよ。営業できなくなったら困りますし(笑)。
くっつー:なるほど!テナントさんの契約書にも「基本的なトラブルは自分で解決してね」って書いてあったりしますもんね。
やまや:はい。特にチェーン店なんかは社内ルールもあって、何かあったときの対応方法が決まっているんで、管理会社に頼らずに運営できちゃうんですよね。

店舗物件は住居と異なり、契約上テナント側の自己解決を前提とする内容が多く含まれています。特に1~2店舗規模では、自主管理でも手間が少なく、管理会社のコストを削減できる利点があります
大規模施設には管理会社が有効な理由
くっつー:でも、逆に「これは管理会社いたほうがいいな」って物件もありますよね?例えば、10階建てのビルとか、10店舗以上が入っている商業施設なんかは、管理会社を入れたほうが断然スムーズですよね。
やまや:やっぱ共用部のルールとか、さまざまなテナント間の調整が必要になりますよね。
くっつー:そうなんです。2~3店舗くらいまでなら、覚書で入居ルール決めて対応できるんですけど、7~8店舗以上になると、管理の負担が一気に増えるんです。誰が中心になってやるのか、調整が大変なんですよ。
やまや:50店舗とかの施設なんて、もう素人じゃ無理ですよね(笑)。
くっつー:はい(笑)。さすがにその規模になると、共用部の清掃やトラブル対応、契約更新の調整など、プロの管理会社が入らないとまわりません。

店舗数が増えると、個別対応が難しくなり、調整役としての管理会社の必要性が高まります。共用部分の運用や、複数テナント間の調整など、管理負担は物件の規模に比例して増加します
管理会社を入れるべきか?判断のポイント

店舗物件の管理は、物件のタイプや規模、トラブル発生の頻度によって大きく異なります。ここでは、管理会社を導入すべきかどうかの判断ポイントを具体的に見ていきます。
管理会社が必要な物件の共通点とは
やまや:やっぱり「この物件は自主管理でOK」「これは管理会社必要」って分かれますよね。たとえば「マンション1棟の1階が店舗になっている」ってケース、よくあるじゃないですか。
くっつー:そうすると、店舗部分だけちゃんと管理されない、っていうことも起きそうですね。
やまや:ああ、住宅の中に店舗が一部あるやつですね。ああいう物件の場合は、住宅部分の管理会社がメインなんですよ。で、店舗だけ違う管理会社ってことは基本的にないんです。
くっつー:そうなんです。実際に「駐車場の取り決めが曖昧で、店舗同士がもめた」ってケースもありましたよ。住宅用の管理会社では対応しきれなかったりするんですよね。
やまや:たしかに!そういうときは「店舗に強い管理会社」が必要になってくるわけですね。

住宅兼用のマンション物件では、住宅部分の管理会社が店舗部分の管理に不慣れな場合があります。テナント同士の駐車場利用トラブルなど、店舗特有の課題に対応できるかがポイントです
管理会社に頼んだことで起きた問題事例
やまや:でも管理会社に任せれば全部安心!ってわけでもないんですよね?
くっつー:はい。実は「管理会社に頼んだけど、店舗のことを全然わかってなくてトラブルになった」って話もあります。
やまや:具体的にどんな問題が起きたんですか?
くっつー:例えば、3店舗入っている1階の物件で、駐車場の取り決めが全然決まってなくて「ここ使えないじゃん!」ってテナント間でケンカになったとか(笑)。
やまや:それ最悪ですね(笑)。住宅目線で管理していると、そういう細かい店舗運営の事情って見落とされがちですもんね。
くっつー:そうなんですよ。やっぱり「管理会社に頼めば安心」というより「どんな管理会社に頼むか」が超大事なんです。

管理会社にも得意・不得意があり、住宅中心の管理会社では店舗のオペレーションに対応できないケースも。特に駐車場や共有スペースに関する調整が不十分だと、店舗間トラブルに発展することがあります。
店舗物件におけるサブリースの可能性
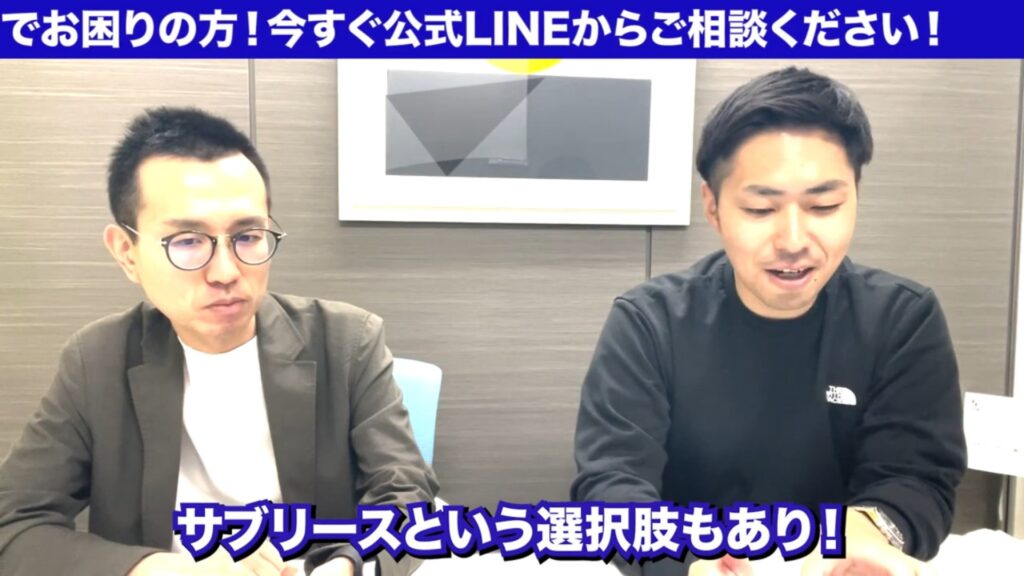
管理会社に頼らず自主管理するか、それともプロに任せるか。もうひとつの選択肢として「サブリース(転貸)」があります。
ここでは、店舗物件におけるサブリースの仕組みと活用方法を見ていきます。
サブリースは悪ではない?メリットとリスクを整理
やまや:ところでくっつーさん、最近「サブリース」ってあまり良い印象持たれてないですよね。
くっつー:そうですね。特に住宅だと「かぼちゃの馬車事件」みたいなトラブルで印象悪いですよね。でも店舗に関しては、必ずしも悪ではないんですよ。
やまや:おっ、ちょっと意外です。
くっつー:たとえば、私たちがサブ管理的に一部だけお手伝いしている物件があるんです。オーナーさんの代わりに、次のテナント探しや契約の窓口業務を私たちが請け負っている感じですね。
やまや:それ、いいですね!オーナーさんにとっては手間が減るし、空室リスクも減らせますし。
くっつー:そうそう。テナントが退去したあと、我々が間に入って必死で次を探します。だってそのままだと我々も家賃が入らないので(笑)。
やまや:なるほど、オーナーとサブリース会社の利害が一致しているわけですね。

店舗のサブリースは、空室リスクを減らしつつプロの知見で運用を委ねられる選択肢です。住宅に比べて賃料変動も小さく、一定の収益を確保しやすいため、ハイリスクな店舗経営の一部を委託できるメリットがあります
住宅と店舗で違う、サブリースの位置づけ
くっつー:でも住宅と店舗じゃ、サブリースの意味合いが全然違うんですね。
やまや:はい。住宅だと「ずっと家賃保証します」って内容が固定されがちで、家賃が相場より下がってもオーナーは変更できなかったりするんですよ。
くっつー:それってけっこう怖いですよね。
やまや:でも店舗の場合、変動リスクはあっても、管理の知識や営業力のある会社がテナント募集を代行してくれるのは大きいです。特に空室が長引くとオーナーさんのダメージが大きいですから。
くっつー:たしかに。逆に言えば「本当に店舗が得意な会社に任せる」ってのが前提ですね。
やまや:そうです。私たちのように店舗専門でやっている会社なら、ノウハウとネットワークがありますし、全国対応も可能ですからね。

店舗のサブリースでは、入居テナントが退去した後の対応まで担ってくれる業者を選ぶことが大切です。住宅よりも管理の柔軟性が高く、専門会社による運用支援がメリットになります
まとめ:店舗物件の管理は「物件規模×オーナーの意向」で決めるべき
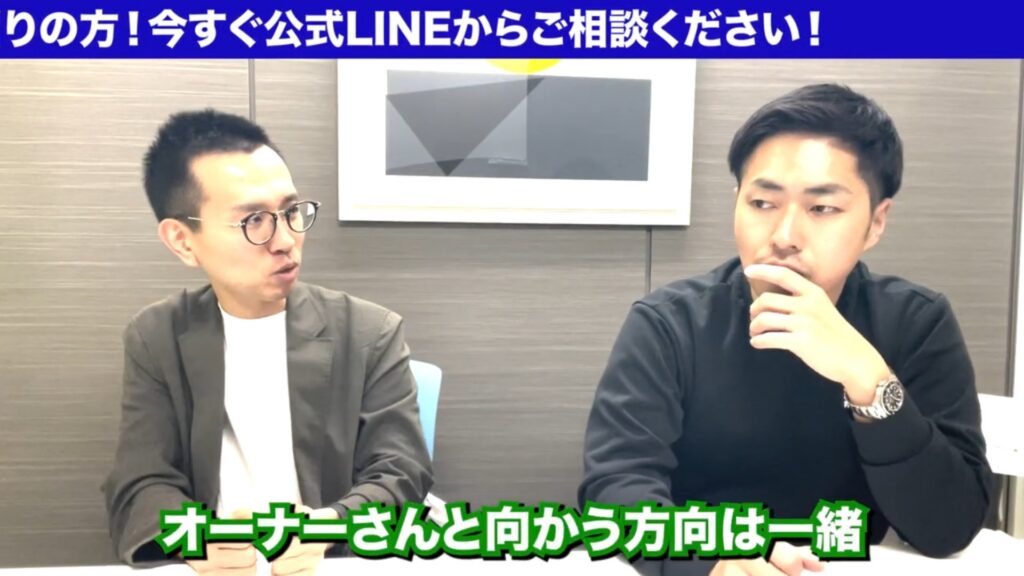
ここまで、店舗物件における管理会社の必要性、自主管理の現実、そしてサブリースの可能性について具体的にお話してきました。最後に、オーナーとしてどんな判断基準を持つべきか、くっつーとやまやが改めて整理します。
くっつー:いやー、改めて思ったんですけど、店舗の管理って「一律でこうすべき」って言えないですね。
やまや:本当にそうです。1~2店舗くらいの小規模なら、自主管理で十分対応できます。余計なコストもかからないし。
くっつー:でも、10店舗以上あるようなビルだったり、共用部分の管理が複雑だったりすると、管理会社がいたほうが楽ですよね。
やまや:はい。そして「自主管理は厳しそうだな」ってときに、サブリースって選択肢を持っておくといいと思います。特に私たちみたいな店舗専門の会社なら、適切な管理やテナント募集を任せてもらえるので。
くっつー:サブリースって聞くとネガティブな印象を持つ人が多いですけど、店舗ならちゃんと機能する仕組みなんですよね。
やまや:はい。要は「自分の物件に合ったパートナーとどう組むか」がすべてなんです。
くっつー:ということで、もし今「自分の物件どうしよう……」って悩んでる方がいたら、ぜひ私たち『テナントの窓口』に気軽に相談してほしいですね。

管理スタイルの最適解は、物件の規模・用途・オーナーの関与意欲によって異なります。自主管理・管理会社・サブリースのいずれも、それぞれのメリットと課題があります。最も重要なのは、信頼できる管理パートナーと長期的な視点で物件運用を考えることです
くっつー:全国のオーナーさん、どんな物件でも店舗専門で対応している『テナントの窓口』が相談に乗ります。
やまや:ぜひ、お問い合わせはお気軽にどうぞ。私たちが全国対応でサポートいたします。
くっつー:本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
やまや:ありがとうございました。
この記事から学べる5つのポイント

この記事では、店舗物件を所有・運営する際に知っておくべき重要な管理スタイルの選択肢を、実際の会話とともに解説してきました。ここでは、オーナーとして押さえておくべきポイントを5つに整理してご紹介します。
1. 自主管理は小規模店舗に最適
1〜2店舗など小規模な物件では、テナント自身がトラブルを解決することが多く、オーナーが対応に追われることは少ないです。余計な管理コストをかけずに運営できるため、自主管理が十分に成り立ちます。
2. 管理会社は規模と複雑性に応じて導入を検討
10店舗以上の商業ビルや、共用部の多い物件では、管理内容が煩雑になりがちです。専門知識のある管理会社を入れることで、オーナーの手間を減らし、円滑な運営が可能になります。
3. 管理会社選びは「店舗に強いかどうか」で決まる
住宅専門の管理会社では、店舗特有の事情(駐車場問題や営業時間トラブルなど)に対応しきれないことがあります。管理会社を選ぶ際は、実績や専門性を見極めることが重要です。
4. サブリースは店舗管理における有効な選択肢
テナント退去後の空室リスクをカバーしつつ、入居者募集や契約交渉も任せられるのがサブリースの強み。特に専門会社と組めば、リスク分散と収益安定が両立できます。
5. 最適な管理スタイルは物件ごとに異なる
管理の正解は一つではありません。自主管理・管理会社・サブリース、それぞれに向き不向きがあり、物件の構造、規模、オーナーの意向に応じて柔軟に選択することが成功の鍵です。
