今回は、店舗オーナーなら誰もが一度は悩む「敷金・保証金はいくらに設定すればいいのか?」というテーマについて、じっくり掘り下げていきます。
住宅賃貸とは違い、店舗の契約では敷金や保証金が高額になりがちで、金額の妥当性を判断するのが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか?私たちも実際に多くのオーナーさんや管理会社の方と話すなかで、この疑問は非常に多く寄せられるものです。
動画内で話した内容をもとに、この記事では金額の設定方法や業種による違い、そして最近の傾向まで、わかりやすくまとめました。テナント誘致の成功にもつながる、大切な条件設定。この機会に一緒に見直してみませんか?
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
敷金・保証金の基準は「6か月」が目安
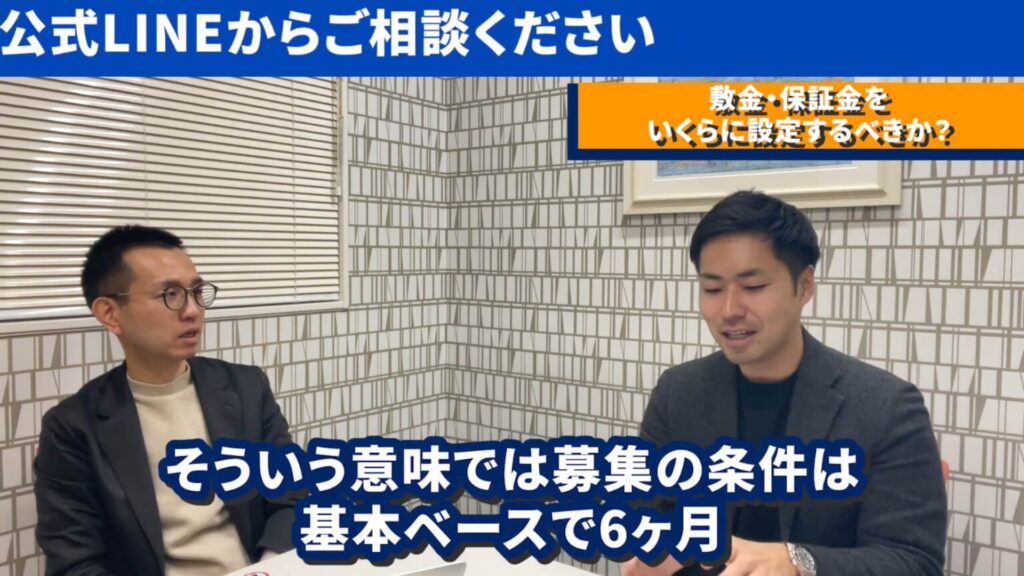
敷金や保証金の金額設定には、明確なルールがあるわけではありません。そのため「ほかの物件と比べてうちは高い?安い?」と悩むオーナーさんも多いはず。ここでは、店舗物件の平均的な敷金・保証金の設定相場と、その根拠について詳しく解説していきます。
そもそも敷金・保証金とは?住宅との違いも解説
やまや:そもそも敷金や保証金って、どういうものか簡単に説明してもらっていいですか?
くっつー:基本的には、入居時に借主が貸主に預けるお金のことですね。何も問題がなければ退去時に返ってくるというのが原則です。
やまや:住宅よりも店舗って敷金が高いイメージがありますけど、実際どうなんですか?
くっつー:そうですね。住宅だと1〜2か月が多いですが、店舗の場合は4〜6か月、場合によっては10か月以上になることもあります。理由としては、内装工事が前提であること、飲食などの業種では設備トラブルの可能性があることなどですね。
やまや:なるほど。店舗はトラブルや原状回復費用が大きくなりがちですもんね。

敷金・保証金は、借主がトラブルを起こした場合や契約違反があった場合に備えてオーナー側が保有する「リスクヘッジ資金」です。店舗契約では、住宅よりも原状回復や修繕の負担が重くなるケースが多く、それを想定して敷金が高めに設定されます。特に飲食や美容系の店舗では設備トラブルや油汚れなどのリスクがあるため、多めに預かる傾向があります
設定金額の相場とその根拠は?
敷金・保証金の「平均相場」はあっても、すべての物件に当てはまるわけではありません。ここでは、なぜ6か月が基準と言われるのか、その根拠を対話形式で掘り下げていきます。
やまや:実際に「いくらに設定すればいいか?」って悩ましいですよね。
くっつー:そうなんです。物件によってまちまちで「この物件は2か月」「こっちは10か月」みたいなこともあります。
やまや:平均的には、どのくらいなんですか?
くっつー:店舗で言うと、6か月前後がひとつの目安になりますね。もちろん業種や立地条件によって変わりますけど、だいたいそれくらいに設定しているオーナーさんが多い印象です。
やまや:それくらいなら、借り手もまだ現実的に払える範囲ですもんね。
くっつー:そうですね。12か月とか言ってしまうと、個人事業主には負担が大きすぎて、かえって借り手がつかない可能性もありますから。

設定金額の目安として「6か月」が基準となる理由は、店舗契約のリスクと現実的な賃借人の資金力を考慮したバランスにあります。近年は大手チェーン店ですら、過剰な保証金を避ける傾向にあり、6か月〜8か月の範囲で調整されることが多くなっています
業種や物件状況によって金額は変動する
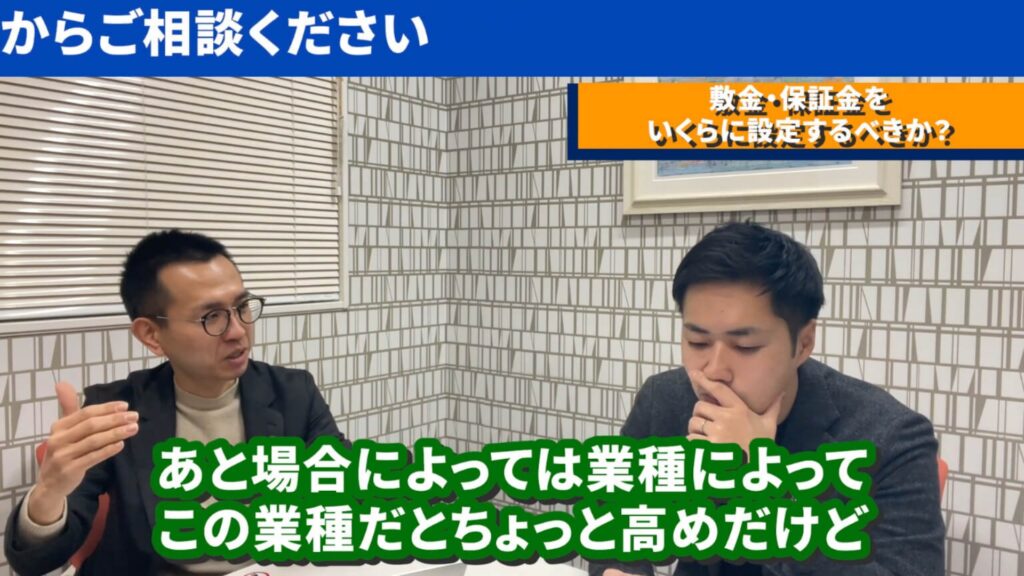
敷金・保証金の「6か月」という基準はあくまで目安にすぎません。実際には、物件の状態や借主の業種によって、大きく金額が変わることもあります。このセクションでは、金額設定に影響する要素を具体的に見ていきましょう。
飲食店やスケルトン物件は高めが基本?
やまや:物件によって全然違うんですね。たとえば同じエリアでも、ある物件は2か月、別の物件は10か月とか。
くっつー:そうなんですよ。特に飲食店とか、美容室みたいな業種は敷金高くなる傾向にありますね。
やまや:スケルトン物件とかだと、内装の手間がかかるから、退去時の原状回復も大変そうですね。
くっつー:そのとおりです。だから12か月とか設定しているオーナーさんもいますよ。最悪のケース、借主が夜逃げして、全部撤去や修繕をオーナーがやらなきゃいけないなんてこともあるので。
やまや:リスクに備える意味で、多めに預かるってことですね。

飲食店や美容系など、設備が複雑でトラブルが起きやすい業種では、敷金・保証金を高めに設定するのが一般的です。また、スケルトン物件(内装がない状態)からの施工の場合、退去時に原状回復が難しいため、敷金12か月などの設定がされることもあります。逆に居抜き物件であれば、内装が残っている分リスクが少なく、若干低めの設定も可能です
個人経営か法人かで異なる設定アプローチ
やまや:借主が個人か法人かでも、設定って変わりますよね?
くっつー:変わります。個人の場合、経営経験が浅かったり、資金面でも不安があるので、リスクヘッジとして高めに設定することが多いです。
やまや:でもそれって、資金力がない人ほど敷金が高くなっちゃうから、少し矛盾してますよね(笑)
くっつー:そうなんですよ(笑)ただ、現実問題として、個人や設立間もない会社の場合は、6か月+2か月など、少し上乗せする形で設定することもあります。
やまや:逆に大手チェーンの場合は、会社の規定で「敷金は8か月まで」とか決まっているところもありますよね。
くっつー:ありますね。だから、募集条件は一律ではなく、借主の属性によって柔軟に対応するのが大事です。

法人と個人では、信用力や資金繰りの安定度が異なるため、敷金・保証金の設定に差が出ます。個人事業主や新設法人の場合、オーナーとしては万が一のトラブルを考慮して、標準よりも高めに設定するのが安全策です。最近では「ペット飼育可」「民泊利用可」などの条件付きで敷金を上乗せするケースも増えており、それを応用した形で業種や属性に応じたカスタマイズも可能です
償却とは?その必要性と注意点
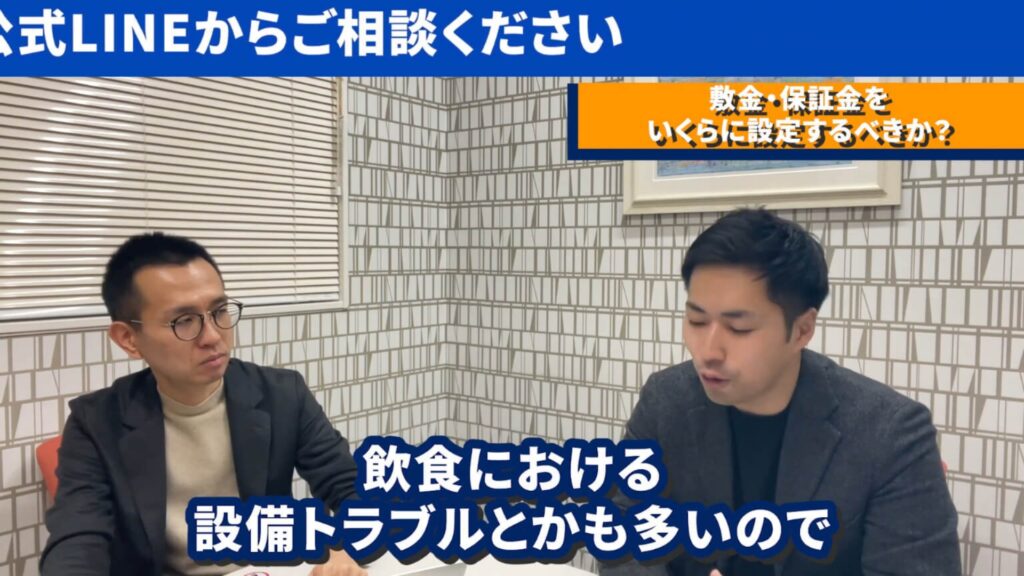
敷金や保証金の設定で、見落としがちなのが「償却」の扱いです。「そもそも償却って何?」「設定する意味あるの?」と感じるオーナーさんも多いはず。ここでは、その仕組みと活用方法について詳しく解説します。
「敷金償却」や「保証金償却」って何?
やまや:よく聞く「償却」って、具体的にどういう意味なんですか?
くっつー:簡単に言うと、預かった敷金や保証金の一部を、退去時に返さずにオーナー側がもらうという仕組みです。返還しない分ですね。
やまや:あれ、でも「敷金償却」って言わないですよね?基本的には「保証金償却」ですよね?何が違うんですか?
くっつー:敷金償却も言いますよ。実は意味はほぼ同じなんです(笑)
やまや:へえ、それって自由に決めていいんですか?
くっつー:はい。特に明確な法律のルールはないので、オーナーさんや不動産仲介会社が自由に設定しているのが実情です。

「償却」とは、預かった敷金・保証金のうち、一定額を返還せずにオーナーが受け取る制度です。例えば「保証金100万円・償却20%」と書かれていれば、退去時に80万円のみ返還されるということです。設備の劣化や原状回復費用を見越して、一定額を償却として設定することで、オーナー側のリスクを軽減できます
償却金額の考え方と入居者への伝え方
やまや:でも、入居者からすると「なんで返ってこないの?」って思いますよね?
くっつー:そこなんですよね。ちゃんと説明しないとトラブルになります。たとえば「この物件は償却20%で、その理由は原状回復費がかかるからです」とか。
やまや:ちゃんと根拠を示しておくのが大事ですね。
くっつー:そうですね。実際に償却を導入しているオーナーさんは、だいたい「内装や設備に使われる費用の一部」として設定してます。
やまや:業種によっても違いそうですね。飲食とかは高そう。
くっつー:まさにそうです。飲食店や民泊、ペット可物件なんかは、償却を設定しておくと後々安心です。

償却を設定する場合は、その理由や金額の根拠を入居者に明示することが大切です。「設備使用に伴う劣化対策」「スケルトン物件の内装撤去」など具体的な用途を説明することで、納得感を得やすくなります。トラブル回避のためにも、契約書や募集条件の段階で明記しておくことが望ましいです
条件設定の工夫で空室リスクを減らす
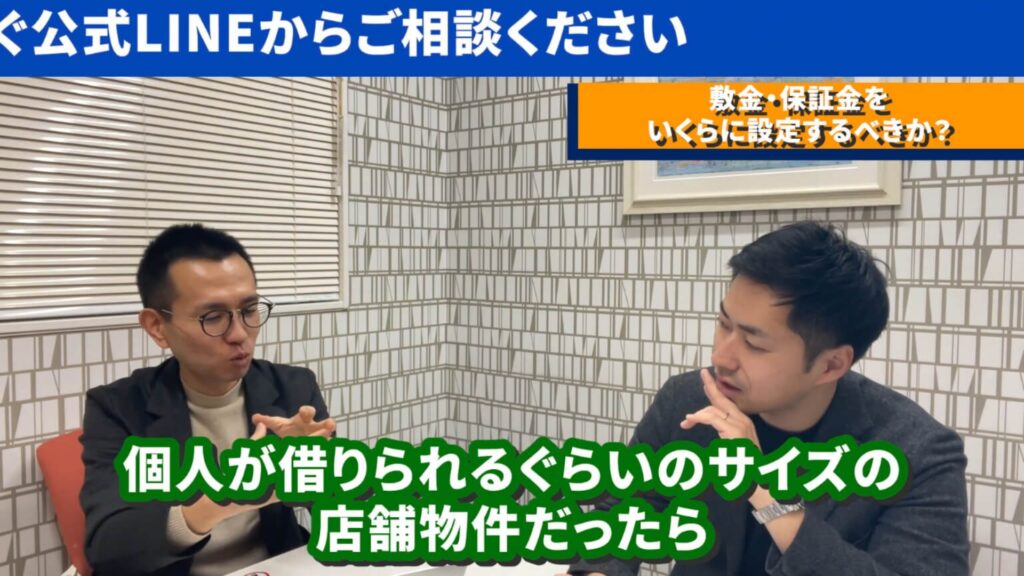
敷金・保証金は高すぎても安すぎても、借り手とのミスマッチを招く可能性があります。柔軟な設定と明確な条件提示が、空室を防ぎ、長く安定した賃貸経営を実現する鍵となります。
条件を一律にせず柔軟な対応が鍵
くっつー:ところで、最初から敷金をガチッと決めてしまうと、問い合わせ自体が来なくなったりしません?
くっつー:ありますね。特に個人事業主の方とかは「敷金が高すぎるから無理」ってなってしまって、そもそも内見すら来ないとか。
やまや:逆に条件を柔軟にしておけば、交渉の余地があって成約につながることもありますよね。
くっつー:そうなんです。たとえば「基本は6か月だけど、設立から3年以内の企業さんは+2か月」とか、あるいは「属性によって応相談」と記載しておくだけでも変わってきます。
やまや:確かにそれなら、借り手側も「相談できるんだ」と思えて前向きになりますよね。

募集条件を一律で設定するのではなく、入居希望者の属性や状況に応じて調整できる仕組みにしておくと、空室期間の短縮にもつながります。あらかじめ「要相談」「属性により変動あり」といった一文を募集情報に加えておくことで、柔軟性のあるオーナーとして評価され、問い合わせ数が増える可能性があります
ペット可や民泊OKなど条件付き加算の事例
やまや:最近、民泊物件とかペット可の物件で「敷金3か月アップ」みたいな条件も見ますよね。
くっつー:そうそう。あれ、住宅の賃貸でもペットがいる場合「敷金+1か月」ってルールがあったりするじゃないですか。それと同じ考え方ですね。
やまや:じゃあ、店舗でも「個人の場合+2か月」「飲食業は+3か月」みたいにしてもいいってことですか?
くっつー:全然アリです。逆に言えば、基本は6か月で設定しておいて、属性ごとにプラスすることで、リスクを抑えつつ対応できます。
やまや:でも最初から高く出しすぎると、敬遠されるってこともありますもんね。
くっつー:だからこそ、ある程度の柔軟性を持たせた書き方が重要なんです。「個人事業主は+2か月」など、明記しつつも交渉余地を残すのがポイントですね。

ペット可、民泊OKなど条件付きの敷金加算は、店舗賃貸にも応用可能です。あらかじめベースの敷金・保証金を定めておき、そこに属性や用途による加算ルールを設定することで、リスク管理と入居率向上の両立が可能になります。条件明記と同時に「相談可」「柔軟に対応します」と添えることで印象も良くなります
この記事から学べる5つのポイント
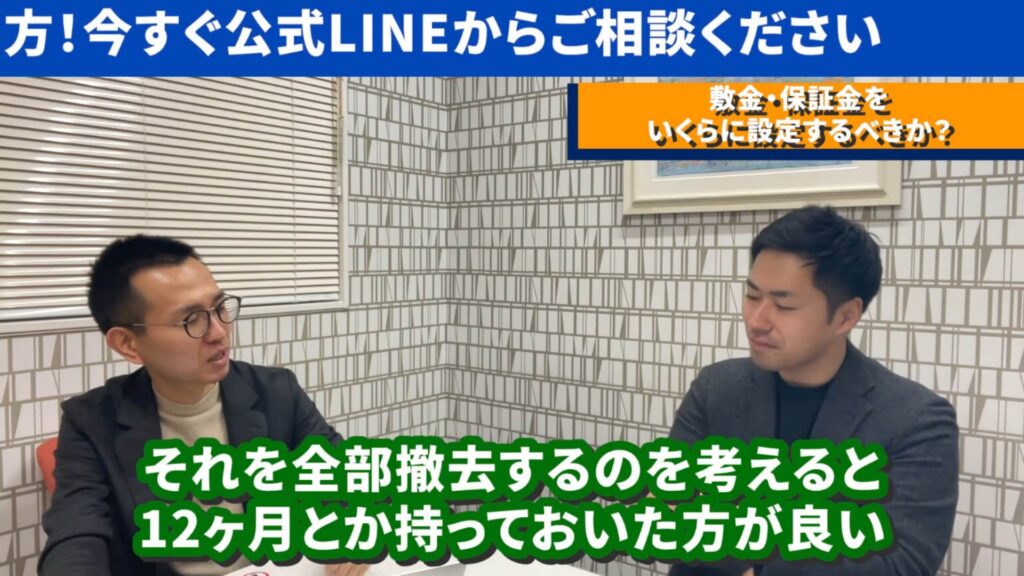
1. 敷金・保証金の相場は「6か月」が基本ライン
店舗物件では4〜6か月が一般的な設定相場となっており、6か月を目安に設定することで借主にとっても現実的かつオーナーにとってもリスクヘッジになるバランスの取れた金額です。
2. 業種や物件の状態で金額は大きく変動する
飲食店やスケルトン物件など、トラブルリスクや原状回復費が高くなるケースでは敷金12か月前後に設定されることもあります。業種ごとの特性を見極めた金額調整がカギです。
3. 借主の属性によって敷金設定を柔軟に対応
個人や新設法人などリスクの高い借主には敷金を高めに設定、大手企業には企業ルールに合わせて調整するなど、属性に応じた柔軟な設定が有効です。
4. 償却設定は明確な理由と説明がトラブル防止に
敷金・保証金に償却を設ける場合は、金額の根拠や用途を明確に説明することが重要です。契約書や募集要項に具体的に記載することで、借主の理解と納得を得やすくなります。
5. 条件付き加算と柔軟対応で空室リスクを回避
ペット可・民泊可・個人事業主対応など、条件に応じて敷金を上乗せする方式は住宅でも一般的です。柔軟な設定を募集情報に盛り込み、交渉可能な姿勢を示すことで入居率が向上します。
