新しくテナント物件を貸し出すオーナーにとって「フリーレントを付けて募集すべきか?」これはよくある悩みです。フリーレントとは、契約から一定期間の家賃を免除する制度。店舗や事務所の場合は、契約後すぐに営業できるわけではなく、内装工事や申請などで時間がかかります。そのため、この制度は借主にとって大きなメリットとなります。
一方で、オーナー側からすると家賃が入らない期間が発生するため、慎重に判断したいところ。本記事では、テナント募集の現場経験豊富な「くっつー」と「やまや」が、実務に即したフリーレント活用のポイントを語ります。
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
フリーレントの基本とテナント物件特有の事情
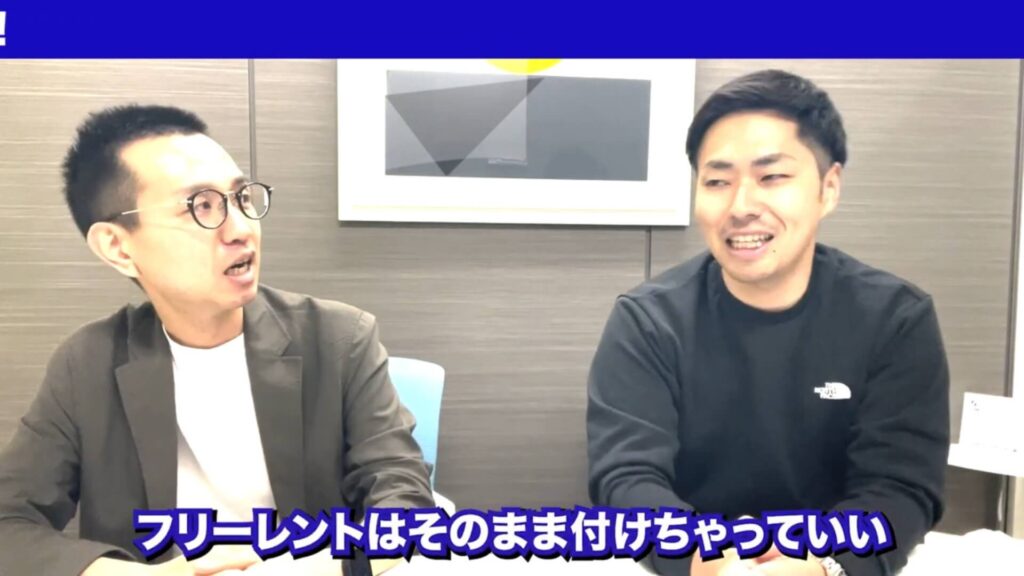
テナント物件では、住宅と違って契約後すぐに営業できるとは限りません。内装工事や行政手続きなどが必要になるため、営業開始までに数週間から数か月の準備期間が発生します。この間、家賃が発生すると借主にとって大きな負担になります。そこで重要なのが「フリーレント制度」です。
住宅との違いとフリーレントが必要な理由
やまや:今日はテナント募集時にフリーレントを付けるべきかどうかって話です。くっつーさん、どう思います?
くっつー:私は必要だと思いますね。住宅と違って、店舗は契約後すぐ営業できないんです。内装工事や許可申請で、どうしても営業開始まで時間がかかります。
やまや:確かに。住宅なら家具を入れれば翌日から住めますけど、店舗はそうはいかないですもんね。
くっつー:そうです。営業できないのに家賃だけ発生すると、借主にとってはかなり負担です。だからフリーレントは必須と言えます。

住宅は入居後すぐに使用可能ですが、店舗や事務所は内装工事や設備投資、行政手続きなど準備期間が必要です。その間の家賃を免除することで、入居者の初期負担を軽減し、契約のハードルを下げられます
内装工事期間と営業開始までの空白期間
やまや:工事期間ってだいたいどのくらいですか?
くっつー:短くても1か月、長ければ2か月以上かかりますね。その間は売上ゼロです。
やまや:その間に家賃20万、30万払うのは確かにきつい……。
くっつー:だからオーナーさんもその期間分は収支に見込んでおくべきなんです。

内装工事の期間は業種によって異なります。飲食店や美容室など設備が多い業態ほど工期が長くなり、営業開始までの空白期間も延びます。この期間を考慮せず家賃を請求すると、入居希望者が契約を避ける原因になります
オーナーが収支に組み込んでおくべき期間の目安
やまや:フリーレントは何か月くらい見込めばいいですか?
くっつー:最低でも1か月、場合によっては2か月です。事前にオーナーさんに伝えてバッファを取ってもらいます。
やまや:そうすれば募集時に慌てず対応できますね。

フリーレント期間は、業種や工事規模によって異なります。事前に見込んで収支計画を立てれば、交渉時に柔軟に対応でき、契約成立率が高まります
募集時にフリーレントを提示するべきか?
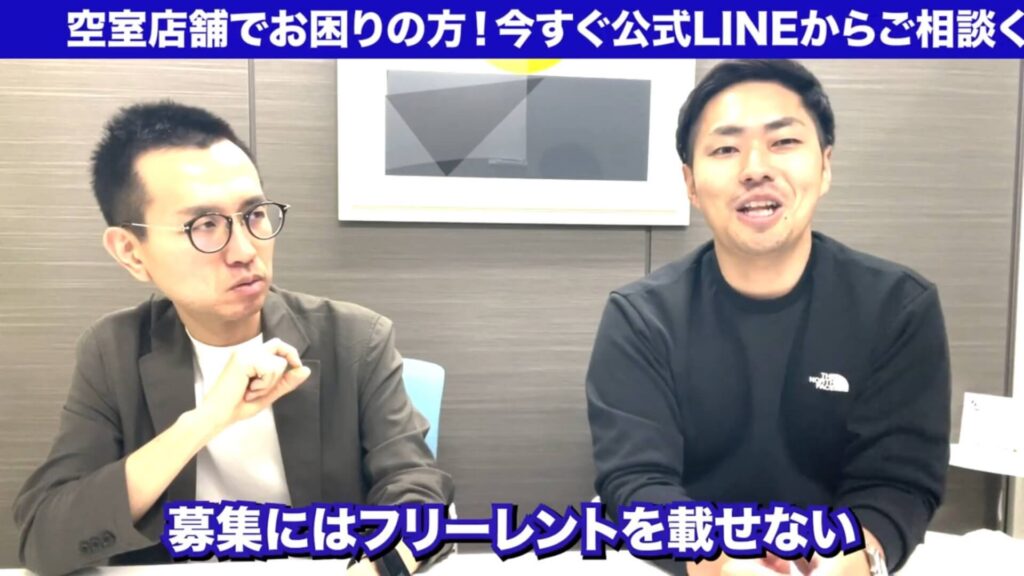
フリーレントは「募集時から条件として提示するか、それとも交渉で出すか」で戦略がわかれます。どちらの方法にもメリットとデメリットがあるため、状況に応じて使い分けることが重要です。
提示しない場合でも必ず交渉される理由
やまや:僕の感覚だと、フリーレントって最初から提示してもしなくても、結局交渉される気がするんですよね。
くっつー:そうですね。提示しなくても、ほとんどの場合は入居希望者から「工事期間中は家賃を免除してほしい」と言われます。
やまや:つまり、募集条件に書いてなくても、契約の流れで話題に上がるってことですよね。
くっつー:はい。だからオーナーとしては、提示するかどうかよりも「何か月までなら応じられるか」を事前に決めておくのが大切です。

フリーレントは募集条件に明記しなくても交渉でほぼ必ず話題に上ります。そのため、オーナーは事前に期間と条件を想定しておく必要があります
最初から提示する場合のメリット・デメリット
やまや:じゃあ、最初から「フリーレント1か月」と出しておくのはどうですか?
くっつー:メリットは、条件が明確になって問い合わせが増える可能性があることです。デメリットは、交渉の余地がなくなり、期間延長を求められることがある点ですね。
やまや:なるほど。交渉カードを失うことにもなるってことか。
くっつー:そうです。募集戦略によって、提示するかどうかは使い分けたほうがいいです。

フリーレントを最初から提示すると集客効果がありますが、交渉の余地がなくなる場合もあります。募集エリアの需要や物件の競争力を見極めて判断しましょう
競合や特殊ケースでフリーレントが不要になるケース
やまや:逆に「フリーレントいらないです」って言われることもあるんですか?
くっつー:ありますよ。例えば競合が多くて人気の物件の場合「すぐに家賃払えます」と言って入居希望者が有利に動くケースがあります。
やまや:それ、オーナーからすると嬉しいですよね。
くっつー:はい。ただ、これはあくまで特殊な条件や市場環境のときだけですね。

人気物件や競合の多い市場では、入居希望者がフリーレント不要を条件に契約を有利に進める場合があります。ただし、一般的なテナント募集ではほぼ必要と考えたほうが現実的です
オーナー目線でのフリーレント活用法
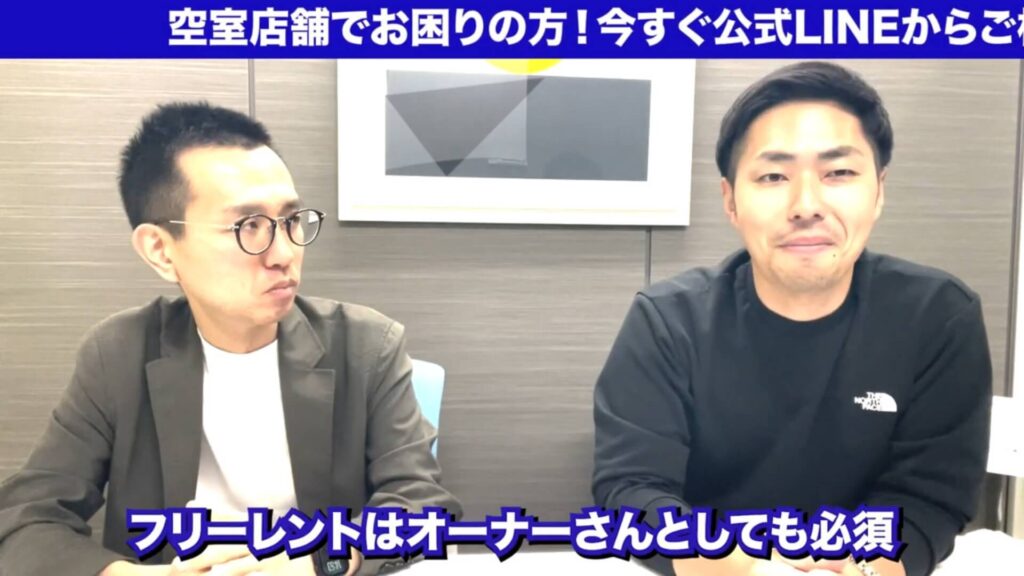
フリーレントは単なる「家賃免除」ではなく、契約成立率を高めるための営業ツールとして使えます。長期的な賃貸経営の安定化にもつながります。
フリーレントを「交渉カード」として使う方法
やまや:くっつーさんは、フリーレントを交渉カードとして使うことはありますか?
くっつー:ありますね。募集時には条件を明示せず、交渉の場で「じゃあ1か月フリーレントにしましょう」と提示することで、相手に特別感を与えられます。
やまや:それは確かに契約をまとめやすくなりますね。

フリーレントを交渉カードとして後出しすることで、相手に「特別に譲歩してもらえた」という印象を与え、契約成立に導きやすくなります
長期的な入居継続を見据えた家賃設定とバランス
やまや:短期的な家賃収入よりも、長期的に入ってもらうほうが大事ですよね。
くっつー:そうです。最初の1〜2か月の家賃を免除してでも、長く入ってもらえれば結果的に安定します。
やまや:オーナーさんにとっても、空室期間が長引くよりはそのほうがいいですね。

短期的な損失よりも長期的な安定を重視することが、賃貸経営では重要です。フリーレントはそのための投資と捉えましょう
民泊・住宅など他業態との比較ポイント
やまや:住宅や民泊ではどうなんですか?
くっつー:住宅はフリーレントがほぼないですね。民泊は借り手が多いので、免除はほとんどしません。店舗は逆にほぼ必須です。
やまや:業態によって全然違うんですね。

住宅は即入居できるためフリーレントは稀です。民泊は需要が高く、借主が有利に動くため免除は少ないです。店舗や事務所は準備期間が必要なため、フリーレントが一般的です
フリーレント設定で失敗しないための実務ポイント

フリーレントはオーナーにとって収入の空白期間を作るため、設定方法を誤ると経営を圧迫します。賃料設定や負担軽減の工夫を取り入れ、募集戦略全体のなかで最適化することが大切です。
賃料バッファの考え方とオーナー負担の軽減策
やまや:フリーレントを出すと、その分オーナーさんの収入は減りますよね。
くっつー:そうですね。でも事前に賃料を少し高めに設定しておけば、免除期間の損失をカバーできます。
やまや:なるほど。募集時からバッファを持たせるってことですね。
くっつー:はい。例えば1か月分のフリーレントを想定して、年間収支でプラスマイナスゼロにする考え方です。

フリーレントの負担は賃料設定で吸収可能です。あらかじめ免除期間を想定し、年間の収支計画に組み込むことで経営リスクを抑えられます
フリーレントを含めた募集戦略の立て方
やまや:募集戦略のなかでフリーレントをどう位置づけるかも大事ですよね。
くっつー:そうです。物件の立地や需要を見て、最初から提示するか交渉カードにするかを決めます。
やまや:需要が低いエリアなら、最初から出したほうがいいかもしれませんね。
くっつー:そうですね。反対に競争力のある物件なら交渉で出すほうが効果的です。

フリーレントは物件の立地・需要・競合状況に合わせて戦略的に使い分けます。事前の市場調査が成功のカギです
テナント探しを成功させるための相談先とサポート
やまや:フリーレント設定って、オーナーだけで判断するのは難しいですよね。
くっつー:そうですね。不動産会社やテナント専門の相談窓口を活用するといいです。私たち「テナントの窓口」でも条件設計からサポートしています。
やまや:専門家に相談すれば、募集条件をより効果的に作れますね。

フリーレントは募集条件全体のなかで最適化する必要があるため、経験豊富な専門家の意見を取り入れると失敗を防げます。「テナントの窓口」のような専門サービスを活用するのも有効です
この記事から学べる5つのポイント
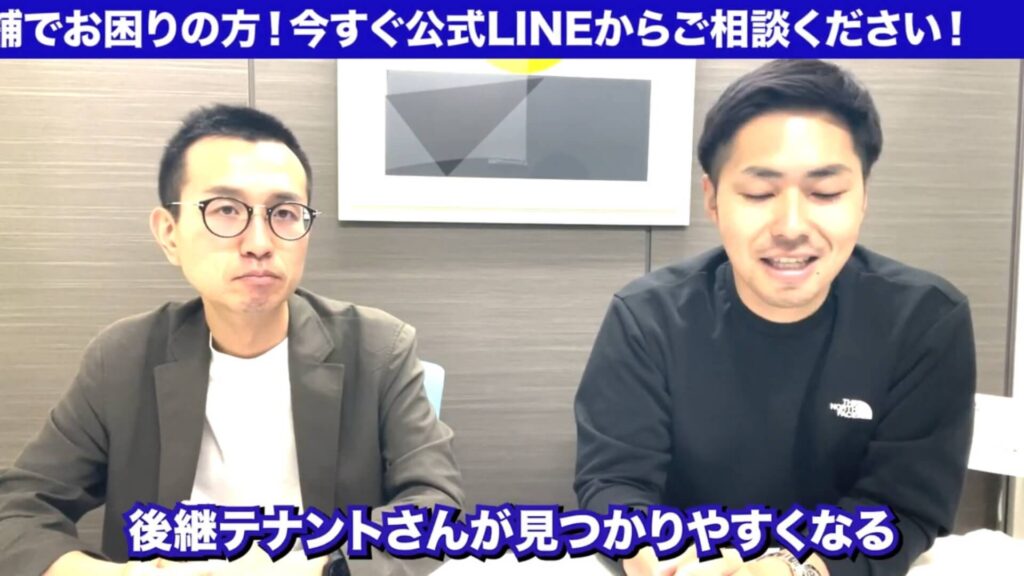
1. テナント物件は住宅と違いフリーレントがほぼ必須
店舗や事務所は契約後すぐに営業できず、内装工事や行政手続きで準備期間が発生します。その間の家賃負担を軽減するため、フリーレントはほぼ必要と考えられます。
2. 募集時の提示は物件の需要に応じて戦略的に使い分ける
需要が高い物件では交渉カードとして温存し、需要が低いエリアや空室期間が長い場合は最初から提示することで集客効果を高められます。
3. フリーレントは短期的な損失より長期的な安定を優先するための投資
最初の1〜2か月の免除は、長期的な入居継続によって回収できます。空室期間を短縮し、契約を安定化させるための有効な手段です。
4. 賃料設定で免除分の負担を吸収する
事前に賃料を少し高めに設定し、年間収支でプラスマイナスゼロにすることで、免除期間の損失をカバーしやすくなります。
5. 専門家のサポートで条件設計の精度を高める
市場調査や競合分析を踏まえた条件設計は、経験豊富な専門家に相談することで精度が向上します。「テナントの窓口」のような専門サービスを活用することで、募集戦略の成功率が高まります。
