「1年以上も決まらない店舗物件、もうどうすればいいの……」
そんなふうに諦めかけているオーナーさん、管理会社の方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
今回は、実際にロードサイドの物件などを数多く扱っている「くっつー」と「やまや」が、1年以上空室が続いてしまう原因とその具体的な対処法を解説します。
「もうダメかも……」と思っていた物件でも、少しの見直しで驚くほど反応が変わることも。長期空室の改善には、特別なノウハウが必要なのではなく「当たり前」をきちんとやり直すことがカギなんです。
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
空室解消の第一歩は「賃料の見直し」
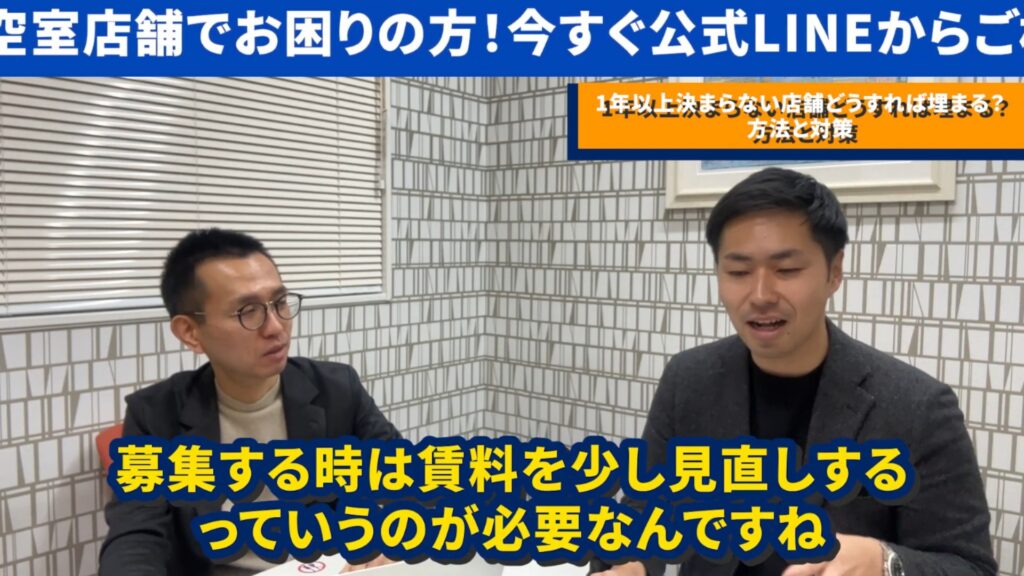
長期間空室が続くと「もしかして立地が悪いのかな……」「もう諦めるしかないのかも」と感じてしまいがちです。しかし、実は“賃料”を少し見直すだけで劇的に反応が変わるケースは少なくありません。ここでは、オーナーさんが最初に取り組むべき賃料調整の考え方と、実際の成功事例についてご紹介します。
賃料が相場より高すぎると検索にも出てこない
くっつー:じゃあまず1つ目のポイント「賃料の見直し」について話しましょうか。実際、賃料が高すぎると物件自体が検索されなくなるって現象がよくあるんです。
やまや:なるほど。つまり、そもそも借りたい人の目にすら触れないってことですね。
くっつー:はい。例えば借り手が「月50万円以下」で検索していたとして、物件が80万円で出ていたら表示されないんですよ。
やまや:それって、いくら良い物件でも見られなければ意味がないですもんね。
くっつー:まさにそうです。だから「1年決まらない」って状態なら、まず早期に賃料を見直すべきですね。交渉を見越して高めに出すのは逆効果になることもあります。
やまや:確かに。入居してもらうことで得られる収入がゼロよりはマシですしね。

賃料は物件の魅力や立地に見合っていないと、検索段階でスルーされてしまいます。オーナー側の希望額ではなく、借り手が「支払える」と思う現実的な価格に調整することが大切です。1年以上決まらないのであれば「一時的な値下げ」で目に触れる機会を作るのが効果的です
実際に賃料を下げた事例とその効果
賃料を下げるという判断は、利益を削るように感じるかもしれません。しかし、実際には「空室というゼロの状態から脱するための投資」と捉えることができます。
ここでは、実際の成功事例を通して、その効果を見ていきましょう。
やまや:実際に賃料を下げて決まった事例ってありますか?
くっつー:ありますね。80万円で出していて1年以上決まらなかった物件を、50万円に下げた途端に問い合わせが一気に来たことがありました。
やまや:え、そんなに反応変わるんですか?
くっつー:はい。借り手側の心理として「ちょっと無理かな」って思った時点で候補から外れますからね。最初から予算内に入っているほうが安心して検討できるんです。
やまや:なるほど。じゃあ「値下げ=損」じゃなくて「収益の最大化」につながるんですね。
くっつー:そうです。空室が続けば続くほど、結局は損ですから。

テナント経営では「高く貸すこと」よりも「継続的に貸すこと」が安定収益に直結します。空室期間が半年~1年続けば、それだけで数百万円の損失になりかねません。賃料を下げる判断は、一見リスクに思えるかもしれませんが、結果的には最善の選択になることも多いのです
効果的な集客方法と不動産会社の選び方
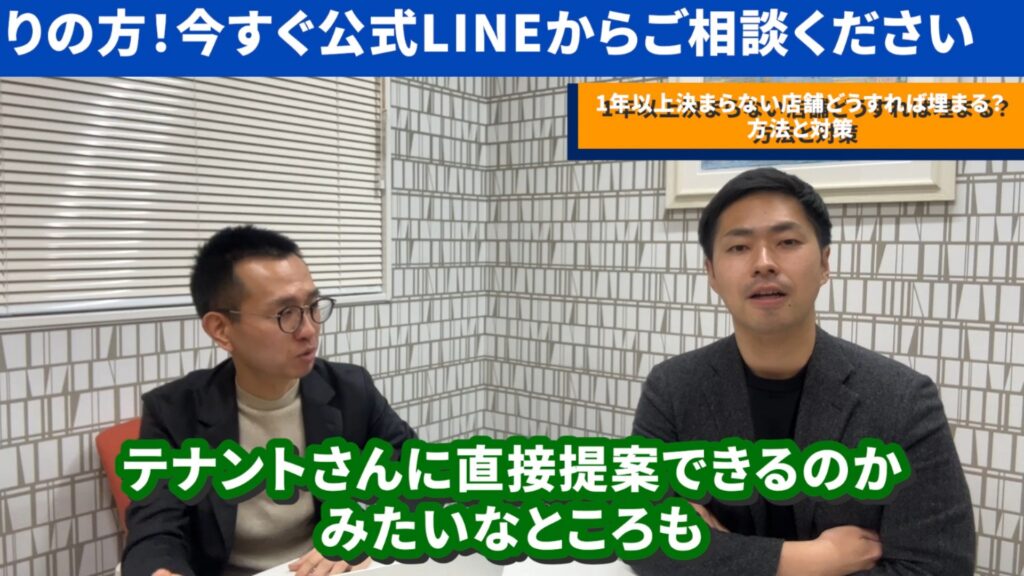
賃料を見直してもなお決まらない場合は「どうやって借り手に物件情報を届けているか」が重要になってきます。情報発信の仕方次第で、どんなに魅力ある物件でも埋もれてしまうことがあるのです。
ここでは、集客方法の見直しと不動産会社選びのポイントを詳しく解説します。
基本的な情報掲出の確認ポイント(貼り紙・アットホームなど)
くっつー:次は集客の部分ですね。意外と多いのが、基本的なことができてないケースです。現地に「テナント募集」の貼り紙すらないとか。
やまや:それ、通りがかった人がいたらチャンス逃してますよね(笑)。
くっつー:そうなんです。まずは「見られていない」ってことに気づいてほしくて、レインズやアットホームに掲載しているかも要確認ですね。
やまや:アットホームもただ出すだけじゃなくて、ちゃんと写真や図面が載ってないとダメですよね?
くっつー:そうなんです。物件写真がない、図面が不鮮明とかだと問い合わせが来ません。逆に、そこをちゃんとしているだけで反応が変わることが多いです。

集客でまず確認すべきは「見られているかどうか」です。貼り紙やネット掲載は基本中の基本ですが、情報の質も重要です。写真や図面の質を上げるだけで物件の印象が一気に良くなり、問い合わせが増えることがあります。掲載先もアットホームやレインズなど、業者向けとエンドユーザー向けの両方を活用することが大切です
対応できる不動産会社を見直すだけで決まるケースも
集客媒体を見直すのと同じくらい重要なのが、依頼している不動産会社の選定です。「付き合いがあるから」といって、住宅専門の不動産会社に任せていませんか?
店舗物件は店舗物件のプロに頼むことで、反応がガラリと変わることがあります。
やまや:やっぱり住宅中心の不動産屋さんだと、店舗の顧客リストとか持ってないですもんね。
くっつー:はい。僕らは、テナントさんと常時やり取りをしています。だからダイレクトに提案できるんです。
やまや:しかも、専任じゃなくても他社にも並行で依頼できるっていうのもポイントですよね。
くっつー:そうそう。店舗は排他的に扱う必要がないので、複数社に頼んでOKです。今の会社だけで決まらないなら、別の会社に声をかけるのも大事。

不動産会社選びは、物件の成約に直結します。住宅中心の会社では店舗のネットワークや専門知識が不足しがちです。対して、テナント専門の会社なら、既に取引実績のあるテナント候補への提案も可能です。複数社への依頼も問題ないため、視野を広げることが空室解消のカギになります
短期貸しで収益化しながら長期入居者を待つ戦略

「なかなか長期で借りてくれる人が現れない……」
そんなときに、空室を活用しながら収益を生む方法の一つが“短期貸し”です。一時的な活用であっても、空室を完全に遊ばせておくよりもメリットは大きく、長期的な入居に繋がることも少なくありません。
短期貸しの実例と活用パターン(展示会・車両置き場など)
くっつー:次のポイントは短期貸しですね。店舗って長期前提で考えがちなんですけど、実は短期でも使えるんです。たとえば車両置き場や物置、展示会やポップアップショップとしての活用もあります。
やまや:え、ポップアップとかでも貸せるんですね?
くっつー:はい、ありますよ。この前も1か月だけ、洋服の展示会として貸してほしいって相談がありました。
やまや:それって賃料安くても、ゼロより全然良いですよね。
くっつー:そのとおりです。例えば50万円の設定を15万円にして3か月だけでも、一旦動くと次に繋がりやすいんですよ。
やまや:なるほど。短期貸しで使われている間に、長期の借り手を探す時間が稼げるわけですね。

短期貸しは、展示会やイベント利用、仮設の倉庫や事務所など、ニーズに合わせて柔軟に対応できます。賃料は相場より大幅に下がりますが、まったく収入がない状態よりは格段に良く、物件の印象も“動いている”ように見えるため、長期入居の検討者にも好影響を与えることがあります
リスクを抑えつつ柔軟な貸し方ができるメリット
短期貸しには「すぐ出ていかれたら困る」という不安もあるかもしれませんが、そこは契約内容でしっかりカバーできます。むしろ「一度でも利用された」実績があることで、長期入居希望者へのアピールにもなるのです。
やまや:やっぱりずっと空いているよりも「今は短期で使われている」ってだけでも印象変わりますよね。
くっつー:はい。空室=不人気ってイメージになりがちなんですが、人が入っていると「使える場所」って認識されやすくなります。
やまや:しかもその間にリフォームとかの判断も後回しにできますしね。
くっつー:そうなんです。焦って手を加えるより、まず短期で活用しながら、次の一手を考える時間を稼ぐのが現実的です。

長期契約にこだわらず短期で運用することで、物件の回転率や収益性が向上します。また、一度短期で使われた物件は「活用実績あり」となり、借り手に安心感を与える効果も。リスクを最小限に抑えつつ、物件を“動かす”ことが何よりの戦略です
リノベーションは待った!“原状貸し”のすすめ
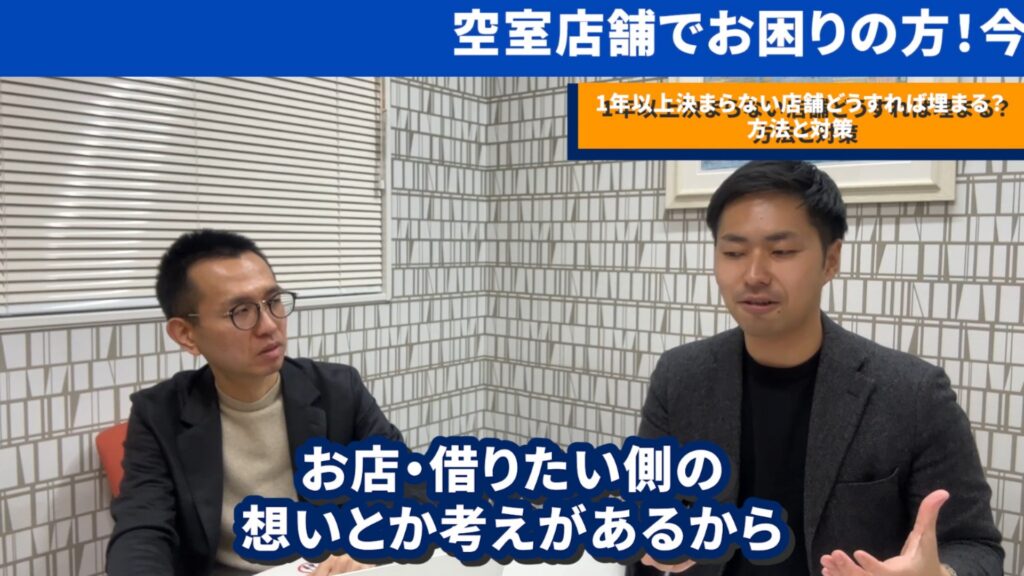
「空室が決まらないなら、思い切って内装をリノベーションしようかな?」
そう考えるオーナーさんも多いのですが、店舗物件においては逆効果になる可能性が高いのです。住居と違い、テナント物件は「借りる側が自分でつくりたいイメージ」を持っているため、貸主の独自リノベはかえって足かせになることもあります。
リノベーションで逆効果になるパターンとは
やまや:くっつーさん、住居ってリフォームしたほうが入居しやすくなるじゃないですか。店舗は違うんですか?
くっつー:結論から言うと、店舗の場合は微妙ですね。場合によってはやらないほうがいいです。
やまや:へぇ、それってどうしてですか?
くっつー:店舗を借りる人って、自分のお店のイメージをすでに持っているんですよ。例えば、キッチンを撤去したほうが良いかなって思って工事しても、飲食店をやりたい人からすると「え、もともとあったのに無くなっているじゃん」ってなるんです。
やまや:ああ、なるほど。先に手を加えることで選択肢を狭めちゃうんですね。
くっつー:そうなんです。貸す側の感覚で「このほうがいい」と思っても、それがニーズに合うとは限らない。だから、最初は“そのまま”で募集するのがベストなんですよ。

住居用物件ではリノベーションがプラスに働くことが多いですが、テナント物件では逆効果になることがあります。テナント希望者は自分の事業に合わせたレイアウトや設備を求めており、既存のリフォームがその自由度を妨げる場合があるからです。「整いすぎた物件」は、逆に敬遠されることもあるのです
借り手のニーズが明確になるまで手を加えない重要性
リフォームは“決まったあとに検討する”という順番が、店舗物件では非常に重要です。具体的なニーズがわかるまでは、内装に手を加えることでかえってマッチングの幅を狭めてしまう恐れがあります。
やまや:じゃあ、問い合わせが来てから条件交渉のなかで「ここだけ直してもらえませんか?」って言われてから動くほうが良いってことですね。
くっつー:そのとおりです。その段階で「じゃあキッチン撤去しますよ」とか「クロス張り替えますよ」とか対応すれば、初期投資も無駄にならないですし。
やまや:なるほど。焦って何かするよりも、まずは見つけてから。そのほうが確実に費用対効果がありますね。
くっつー:そうですね。しかも、内装よりも「立地」と「賃料」で決まることが多いので、中を整えるよりも条件を整えるほうが先決です。

テナント募集では「借りたい人が現れてから手を加える」のが基本です。初期投資の無駄を防ぎつつ、相手の要望にピンポイントで応えることができるため、成約率も高まります。内装よりも先に見直すべきは、立地・賃料・集客方法です
空室対策のまとめと次の一手
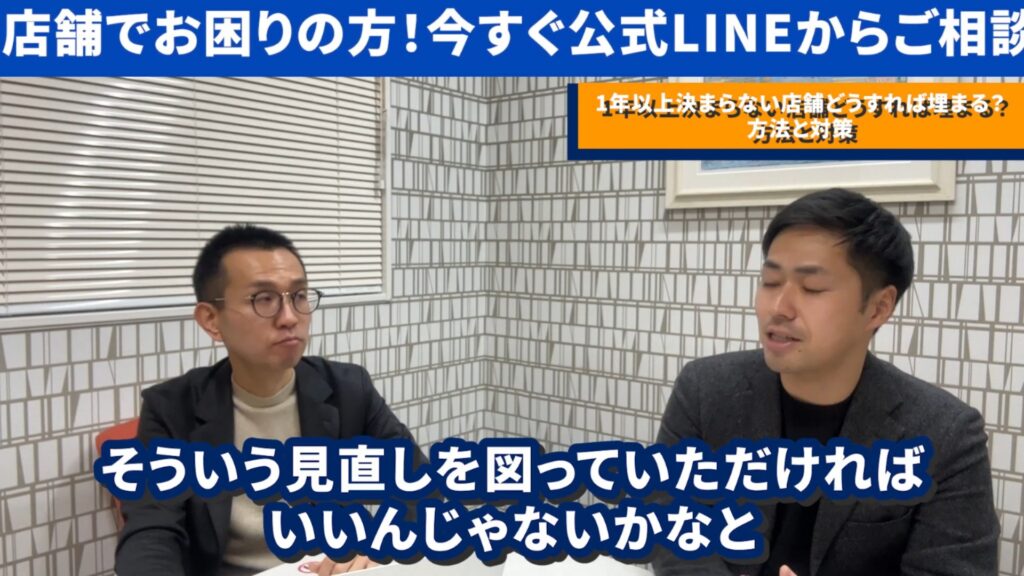
ここまで、1年以上決まらないテナント物件をどうすれば埋められるのかについて「賃料の見直し」「集客方法の改善」「短期貸しの活用」「リノベーションの判断」まで、具体的にお伝えしてきました。
どれも特別なテクニックではなく「当たり前を丁寧にやり直す」ことが空室改善のカギです。これまでうまくいかなかった原因を一つひとつ見直していくことで、今後の打ち手が必ず見えてきます。
成約につなげるための具体的アクション
やまや:最後にまとめとして、読者の方に伝えたいことってありますか?
くっつー:はい。まず、1年も決まらない場合は、そのままでは厳しいと認識することが第一歩です。賃料・集客・貸し方、この3つのどこかに改善の余地があるはずなんです。
やまや:実際、見直しただけで1か月以内に決まるケースもあるって話でしたもんね。
くっつー:そうです。動いている物件には反応があります。ずっとゼロのままよりも、小さくても動きを作る。それが長期成約につながるんです。
やまや:テナントって、タイミングも大きいですもんね。「たまたま空いていた」が成約のきっかけになることもあるし。
くっつー:はい。だからこそ、準備だけはちゃんとしておく。あとは相談できる専門家に頼るのが近道です。

店舗の空室対策に“魔法の一手”はありませんが、どれも再現性が高く、すぐに実行できる内容です。オーナー自身で見直せる部分もありますが、限界があるなら「テナント専門の会社に相談する」ことが最短ルートとなります。「テナントの窓口」では、具体的な物件情報に基づいて戦略をご提案可能です
この記事から学べる5つのポイント
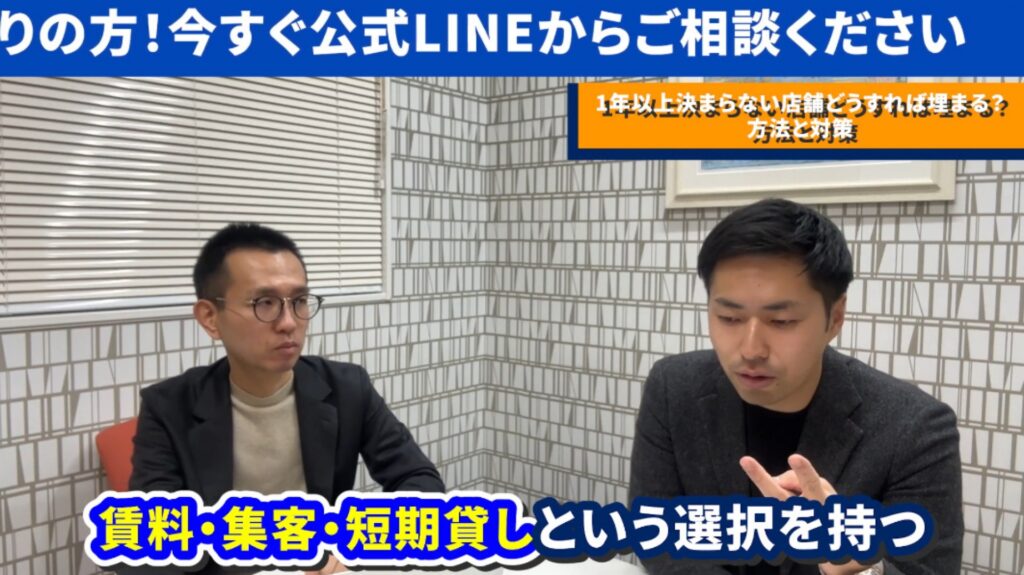
1. 賃料は「相場に合わせる」が基本、検索されない価格は意味がない
高すぎる賃料設定は、借り手の検索条件にすら引っかからず、存在しないのと同じです。適正価格まで下げることで、初めて「比較対象」として検討してもらえるようになります。
2. 見られる情報の質で決まる!写真・図面・掲示物の徹底強化
どれだけ良い物件でも、情報が届いていなければ借り手には選ばれません。現地の貼り紙、ネット掲載の写真と図面など「見た目の情報」の強化で反応は大きく変わります。
3. 不動産会社の見直しは必須!店舗専門会社の活用で結果が出る
住宅メインの不動産会社では、店舗ニーズに応えきれないことも。テナント専門会社に切り替えるだけで、既存の顧客リストを活かした提案が可能になります。
4. 短期貸しは“動かす”戦略!収益と集客の両立ができる
空室期間を短期貸しで埋めることで、ゼロ収入を防ぎ、借り手の印象も良くなります。展示会・倉庫・車両置き場など一時活用でも実績となり、次に繋がりやすくなります。
5. リノベーションは後回し!“そのまま貸す”ことが意外と正解
テナントは自分で内装を作りたい人が多いため、貸主による先回りの改装は逆効果になることも。まずは借り手が現れてから、そのニーズに合わせた改修対応をおこなうほうが、費用も無駄になりません。
