こんにちは、テナントの窓口の「くっつー」と「やまや」です!
今回は、店舗オーナーや貸主の皆さんにとって直球で気になるテーマについてリアルな声を交えながらお届けします。それは、なぜ今、テナント倒産が急増しているのか?という問い。実は、近年の人件費や資材費の高騰に加え、人手不足の状況が過去にないほど深刻になっており、その結果として経営が立ち行かず店舗を手放すケースが増えているのです。
この記事では、倒産が増えている「本当の理由」を、くっつーとやまやが対話形式でわかりやすく掘り下げます。
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
テナント倒産が急増中!その背景と現場の実情
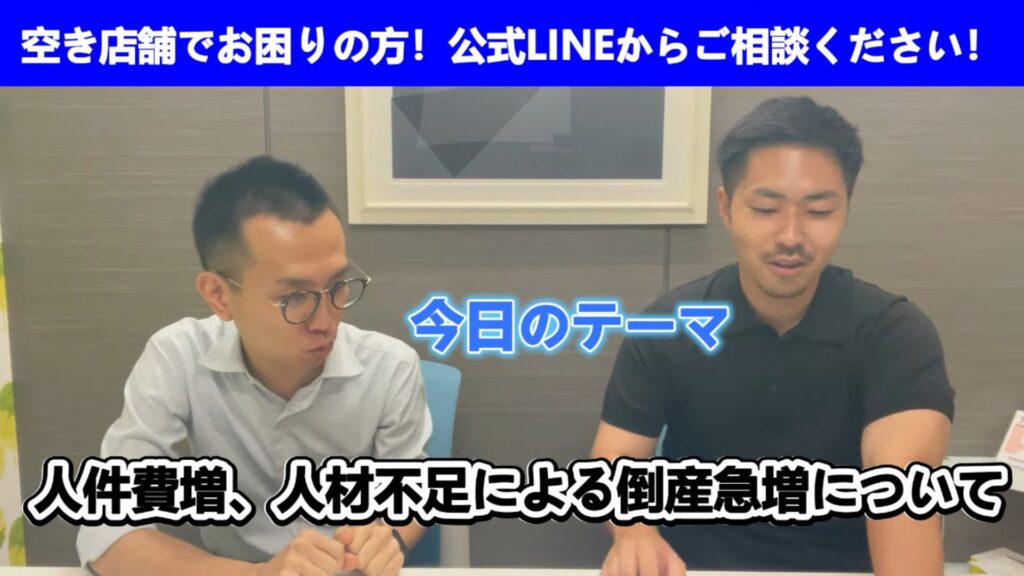
近年、店舗ビジネスを取り巻く環境は厳しさを増しており、倒産リスクが目立つようになっています。では、その原因は一体どこにあるのでしょう?現場のリアルな声をヒントに紐解いていきましょう。
人手不足が過去最多の倒産理由に
やまや:今日は何の話にしましょうか?
くっつー:今回はですね「テナントの倒産が増えている」っていうテーマで話していきたいなと思ってます。
やまや:それ、確かに最近よく耳にしますね。倒産が増えている背景には何があるんですか?
くっつー:大きな要因のひとつが「人手不足」なんですよ。日経新聞にも出てましたけど、倒産理由のなかで過去最多を記録したのが人手不足だったらしくて。
やまや:飲食店とかでもよく見ますよね。「スタッフがいないため臨時休業します」みたいな貼り紙。
くっつー:そうそう。しかも、ただ人がいればいいって話でもなくて、例えばピラティスのインストラクターとかは資格が必要だったりするじゃないですか。
やまや:あー、それは確かに。働けるだけじゃなくて「資格持ちじゃないとダメ」って条件があるんですね。
くっつー:そうなんですよ。だから単純な人手不足じゃなくて「即戦力で資格もある人がいない」っていう問題も重なっているんです。

現在の人手不足は単なる「アルバイトが集まらない」というレベルではなく、資格やスキルが求められる専門職でも採用が困難になっています。特に飲食・フィットネス・美容業界ではこの傾向が顕著で、テナントとして営業を維持できないケースが増えています
人件費・資材高騰が経営を圧迫
やまや:人が足りないだけでも大変なのに、人件費自体も上がってますよね?
くっつー:そうなんですよ。それに加えて資材や材料費も高騰してますからね。もうダブルパンチです。
やまや:でも、商品価格に転嫁しようとしても難しいって話、よく聞きます。
くっつー:まさにそれです。例えばラーメン屋さんで1杯1,000円を超えると、お客さんが来なくなるんですよ。
やまや:確かに、それ超えると「高い」って感じちゃいますもんね。
くっつー:だから結局、材料費や人件費が上がっても、値上げできない。利益が出ない。結果として、耐えきれずに閉店するっていう悪循環です。
やまや:なるほど。店舗側だけが損を被っているような構造ですね。
くっつー:そうです。だから、飲食店なんかは特にリスクが高くて「10年で8割潰れる」って言われているんですよ。それが今はもっと加速していると思いますね。

飲食店など価格上限が明確な業態では、コスト増加を販売価格に反映できないという課題があります。さらに、立地に応じて賃料も上昇傾向にあり、家賃・人件費・材料費のトリプルコストが経営を圧迫しています
無人業態は本当に有効?リスクと実情

人手不足への対策として「無人業態」が注目されています。しかし、現実には「完全に人を介さない店舗運営」は本当に可能なのでしょうか?現場の実体験を交えながら、その課題とリスクを深掘りします。
無人店舗にも「人手」は必要だった
くっつー:人手不足のなかで、無人店舗ってどうなんですか?最近よく聞きますよね。
やまや:そうですね。一時期「無人餃子」から始まって、今はスイーツや古着、さらには肉まで無人で売っているお店も増えてますね。
くっつー:人がいらないからコストもかからないって思っちゃいそうですが……。実際はそんなに単純じゃないんですよ。無人っていっても、商品の補充とか入れ替えは必要で、朝10時から夕方16時くらいの間に誰かが作業しないと回らないんです。
やまや:それだと結局、人が必要なんですね(笑)。
くっつー:はい(笑)。完全に人手ゼロっていうのは難しいです。オーナーさん自身が対応するならいいですが、別で人を雇うなら手間やコストは思ったほど減りません。

「無人業態」と呼ばれる店舗でも、商品の管理・補充・清掃など運営に人が関わる工程が多くあります。完全無人を実現するには、専用システムや高額な設備投資、効率的な物流体制が不可欠であり、実際には「省人化」に近い形がほとんどです
オーナーが避けるべき無人業態とは?
やまや:でも、無人店舗ってオーナーさん側からの評判はどうなんですか?
くっつー:けっこうアレルギー持っている方、多いですね。特にセキュリティ面の不安を感じる方が多いです。
やまや:ああ、たしかに。ドアが開けっぱなしで誰でも入れるってなると、怖いですよね。
くっつー:そうなんです。会員アプリで解錠する仕組みとか、監視カメラがあるようなシステムがあればまだ良いですが、そうじゃない無人店舗は「トラブルの元になる」って敬遠されがちです。
やまや:完全無人よりも、少し人が関わっているほうが安心感ありますね。
くっつー:オーナー目線では「防犯・管理がしっかりしているか」はかなり重要なポイントです。ガラッとドアが開いて、誰もいない状態って、やっぱりちょっと不安ですよね。

無人店舗の導入には、防犯や安全面への対策が不可欠です。テナントオーナーとしては「きちんと管理が行き届く仕組みがあるか」「近隣店舗との調和が取れるか」といった視点で判断する必要があります
これからのテナント運用で失敗しないために

店舗ビジネスを取り巻く環境が大きく変化するなかで、テナントオーナーがとるべき判断基準も進化しています。このセクションでは、どのような業態や借主を選ぶべきか、そして今後の貸し出し戦略のヒントについて考えていきます。
少人数運営がカギ!業態選びの新基準
やまや:やっぱり、これからは人が少なくても回せる業態がポイントになってきますよね。
くっつー:そうですね。特に今後は「少人数でもオペレーションが成立するかどうか」が大事になってくると思います。
やまや:オーナーさんも、貸す相手の業態を見極めないといけませんね。
くっつー:そうです。個人的には「自分ひとりで運営します!」っていう方には期待できますね。マンパワー一本でやり切る覚悟のある人ですね。
やまや:逆に「ほかにも本業があって初めて店舗経営やります」みたいなケースはちょっと危ないかもしれないですね。
くっつー:そうなんです。結局、人を雇わなきゃいけないし、でも人材は不足しているし、ってなると詰むんですよね(笑)。
やまや:(笑)。なるほど、運営力と覚悟がセットじゃないと厳しいんですね。

少人数運営に対応できる業態は、今後のテナント運営における生き残りのカギとなります。オーナーとしては「スタッフ数に依存しない業態」や「オーナー自身が回せるモデル」に注目するのがポイントです
オーナー視点で重要な「相手企業の体力」とは
くっつー:そうなると、借りる側の企業の「体力」も見極めが必要になりますね。
やまや:はい。特に大きい店舗を貸す場合は、やっぱりある程度の企業規模がある会社じゃないと厳しいです。
くっつー:実際、以前閉店したお店で後テナントをつけたときも、前の事業者は小規模チェーンだったんですよね?
やまや:そうです。10店舗くらい持っていたチェーンだったんですけど、社員やアルバイトが辞めていって、最終的に人手が足りなくなって閉店に至ったそうです。
くっつー:売上が良くても、運営が回らなければ意味ないですもんね。
やまや:だから、大きなスペースを貸す場合は、大手企業とか運営力のあるところに提案するのが安全だと思います。私たちはそういう企業にも提案できるツールを持ってますし、気軽に相談していただけたらと思ってます。
くっつー:ほかの不動産会社にお願いしてても、併用して相談していただけると選択肢が広がりますよね。
やまや:はい、もちろんです。とにかく「失敗しないための選択肢」を一緒に考えたいと思ってますので、遠慮なくご相談ください!

オーナーがテナント選定時に注目すべきなのは「集客力」や「事業内容」だけではなく「運営体制」や「企業の持続力(体力)」です。特に大型区画の場合、企業規模や人材確保力が安定運営の重要な指標になります
この記事から学べる5つのポイント

1. 人手不足は今や「倒産理由No.1」の時代に突入
人手不足が原因で倒産するケースが過去最多を記録しています。飲食やフィットネス業界では、単なる人材不足ではなく「資格持ちの即戦力がいない」ことが深刻化しており、オペレーションそのものが回らなくなる店舗が続出しています。
2. 人件費・材料費の高騰が経営を直撃
近年、最低賃金の上昇や資材価格の高騰が止まらず、これまでの利益構造が維持できない店舗が増えています。値上げしたくても価格競争が激しいため転嫁が難しく、経営圧迫の要因となっています。
3. 「無人店舗」は万能ではない。むしろ人手が必要な場面も
無人業態は省人化には効果的ですが、完全な無人化は現実的ではありません。商品補充や清掃、在庫管理など、人の手が必要な作業が残るため、初期のイメージほど簡単ではない点に注意が必要です。
4. 少人数運営に適した業態こそ生き残る
オーナー自身が運営に関与できる、もしくは最低限の人数で回せる業態が今後の主流です。人材確保に頼らないビジネスモデルが、経営リスクを抑える鍵となります。
5. 借主の「企業体力」を見極めることが重要
物件を貸し出す際は、借主の事業内容や集客力だけでなく、継続的に人材を確保し店舗を維持できる「企業としての体力」も重視すべきです。特に広めの物件では、安定した運営力を持つ企業とのマッチングが求められます。
