「建物ができてからテナントを探す」そんな常識を覆す、建築前から動くテナント戦略とは?今回ご紹介するのは、まだ建物が完成していない段階でオーナーや事業者から寄せられた「この立地で、どんな店舗を誘致すべき?」というリアルな相談事例です。
テナント募集において「建築計画段階での相談」がなぜ重要なのか?どのように賃料設定をおこない、テナント候補を絞り込むのか?現場で実際におこなわれているやりとりを、くっつーとやまやが詳しく解説します!
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
建築中から始まるテナント戦略!実際の相談事例とその成果

建築が始まってからでは遅い?今回は、建物の完成前に寄せられた具体的なテナント相談事例を通じて、計画段階からテナント誘致をおこなう重要性と、その効果について掘り下げていきます。
建築中に相談が来た!駅近物件に合う店舗と賃料設定を提案
くっつー:はいよろしくお願いします。今日はよくある建築計画に関する相談について、最近あった実例を交えて話せたらと思ってます。
やまや:よろしくお願いします。最近、交流会などで多くの方にお会いする機会がありました。初対面の方と1日に4件くらい面談することもあるんですけど、先日土地から建物を建てるという会社の方とお話しました。
くっつー:あー、土地探しからやるパターンですね。
やまや:そうです。その会社さんは今まで住宅メインでやっていたんですが、駅近などの立地だと1階を店舗にしたほうが賃料も取れるということで、最近になって店舗もやり始めたそうです。
くっつー:でも住宅中心だったから、店舗賃料の相場とか、どういうテナントが入るかは全然わからないという感じですよね。
やまや:まさにそのとおりで「この立地でどれくらいの賃料にしたらいいのか」とか「この物件にどんなテナントが来てくれるのか」っていう相談をいただいたんです。
くっつー:そういうケース、意外と多いですよね。
やまや:多いですね。建築中の物件で賃料設定に悩んでいる方ってすごく多くて、しかも新築だと相場が倍以上になることもある。だから難しいんですよ。
くっつー:確かに、既存の建物なら賃料の基準がわかりやすいけど、新築だと読めないですよね。
やまや:そうですね。特に商業に慣れていない会社さんだと、隣の駅前が坪単価5万円とか6万円でも、実際にテナント提案してみると2〜3万円でしか反応がない、ということもあります。

このように、建築中の物件におけるテナント相談は、賃料相場の把握や想定する業種の絞り込みが極めて重要です。駅近など一見好立地でも、賃料が高すぎればテナントは決まりません。特に、住宅から店舗に初めて転換するデベロッパーやオーナーは、事前に専門家と連携することがリスク回避に繋がります
新築でも「賃料2万円」?リアルな相場感と提案のタイミングとは
くっつー:ちなみに、やまやさんがそのときどうやって賃料を提案したのか、もう少し詳しく教えてもらえますか?
やまや:はい。その時は、まず今募集中の物件の情報や、これまで成約になった過去のデータをもとに相場感を整理しました。それに加えて、日々テナントさんとやり取りしているなかで「この条件なら検討する」といったリアルな声も集めていたので、それを踏まえて提案しました。
くっつー:なるほど、理論じゃなくて現場の声も反映しているんですね。
やまや:そうですね。今回の物件は坪数が20坪くらいで、住・飲食はNGという条件だったので、物販かサービス系に絞って、この辺の業種がいいんじゃないかという形で提案しました。
くっつー:で、結果的にその提案がどのくらい刺さったんですか?
やまや:私が提案した賃料のちょうど中間くらいで「じゃあこの金額で募集かけてもらえますか?」って、すぐに回答いただきました。
くっつー:すごいですね。それまで募集してなかったわけですよね?
やまや:はい。それまで具体的な募集はしてなかったんですが、私から提案したことで「これは検討に値する」と判断していただき、水面下で紹介を始めました。

新築物件は特に「いくらで貸せるのか」が読みにくく、相場のブレも大きいです。たとえば既存の建物では坪単価2万円だったのに、新築だと4万円以上を狙うケースもあります。しかし、テナント側の視点では、賃料が高すぎると契約を見送ることも多いため、オーナーの想定と乖離が起こりがちです。このギャップを埋めるためには、リアルタイムの市場感とテナントニーズを知る専門家の提案が不可欠です
計画段階からテナントを決める企業の戦略とは?
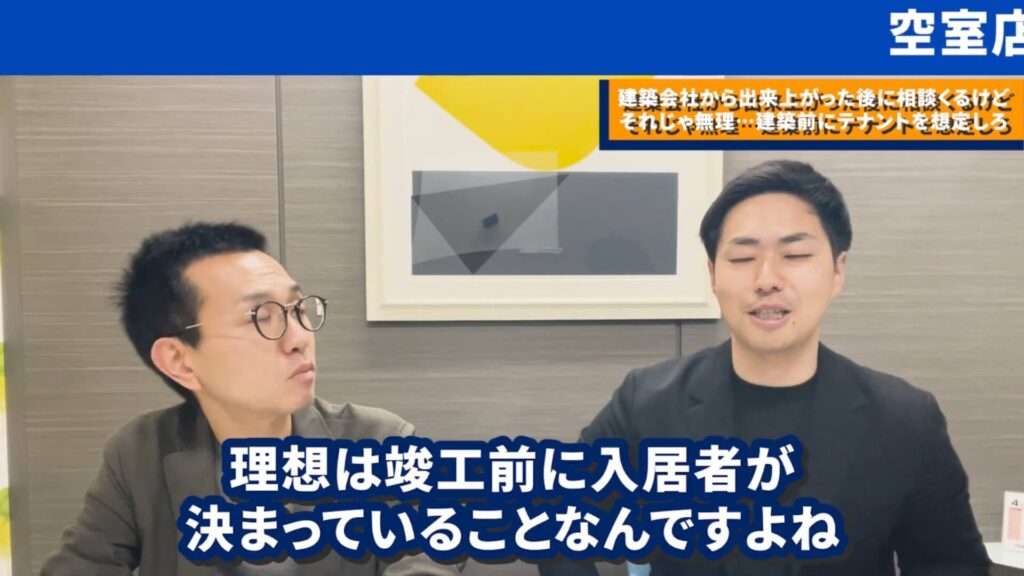
計画段階からテナントを決めて動く企業が増えています。完成前に契約を交わすことで、収益化のスピードを高め、空室リスクを回避できるこの手法について、具体的な違いやリスクヘッジのポイントを見ていきましょう。
計画段階からテナントを決める企業と、あとから動く企業の違い
くっつー:私がいた会社は、逆に「誰に貸すかを先に決めてから建物を建てる」スタイルでした。1階には誰、2階には誰、みたいに。
やまや:その話を聞いていると、くっつーさんの元いた会社ってかなり計画的だったんですね。それってもう2年後とか3年後とかの入居者を決めているってことですよね?すごい先読み。
くっつー:はい。実際に2年後とか、それ以上先でも契約を進めてました。仮契約ではなく、正式な賃貸借契約として。
やまや:えっ、もうその段階で契約書も作るんですか?
くっつー:はい。建物が建つことを前提に、契約書を交わします。名前は「予約契約」でも「賃貸借契約」でもどちらでもよくて、とにかく法的にも有効な形で結びます。
やまや:じゃあ契約したあとにキャンセルするのは無理ってことですね?
くっつー:そうです。契約書には「開業前に解約した場合のペナルティ」をきちんと盛り込んでるので、基本的に解約できません。たとえば2年後、仮にコロナみたいな不測の事態があっても、契約は契約です。
やまや:それってリスクはありますけど、テナントが確定している分、計画がブレないという強みはありますね。
くっつー:そうなんです。ただ、世のなかの9割以上は建物が建ってから募集するスタイルだそうです。うちの会社はかなり先行型だったと思います。

テナントを「建物が完成してから探す」か「計画段階から決める」かで、事業リスクと収益安定性は大きく変わります。前者は賃料相場の変動や空室リスクに対応しやすい反面、タイムロスや条件不一致のリスクがあります。一方、後者のように事前に契約を交わす企業では、建築完了と同時に収益が立ち始めるため、効率的かつ計画的に事業が進められます
失敗する賃料設定と長期空室リスクの実例
やまや:でも実際には、建物が完成してからテナント募集するケースのほうが多いわけですよね?
くっつー:そうですね。建物が完成してから「このぐらいの賃料でいけるかな」って感覚で募集を始めるところが大多数です。
やまや:感覚って危ないですよね。実際、うまくいってない例もあったりしますか?
くっつー:めちゃくちゃありますよ。最近だと港区で2年経ってもテナントが決まっていない新築ビルがありました。AD(広告費)を12か月付けても決まらない状態でした。
やまや:12か月って相当ですよね!建てちゃったけど、蓋を開けてみたらその賃料では入らなかったってことですよね。
くっつー:そうです。もともと坪4万円くらいで見込んでたのに、実際は2万円でも決まらなかった。完全に読み違えてますよね。
やまや:そういう例を見ても、やっぱり事前にどれくらいの賃料なら需要があるか把握しておくことって大事ですね。
くっつー:本当にそうです。建物が完成してからだと、決まらないまま何か月、下手すれば何年も空室ってリスクがあるので、できるだけ早い段階で相談していただけると助かります。
やまや:着工前、もしくは最低でも建築中の段階から動き出せると、かなり状況は変わりますよね。
くっつー:そうですね。建物が見えてきた頃に動き出すのがベストです。今回の相談も、完成前に動き出したことで、スムーズにテナント提案ができました。

テナントが決まらず長期空室になると、オーナーにとって大きな機会損失になります。特に新築物件は投資額も大きく、賃料設定を誤ると取り返しがつきません。事前にマーケットリサーチと専門家の意見を取り入れることで、適正な賃料設定と早期成約の可能性が高まります
建築前の相談が未来を変える!成功事例から学ぶテナント戦略
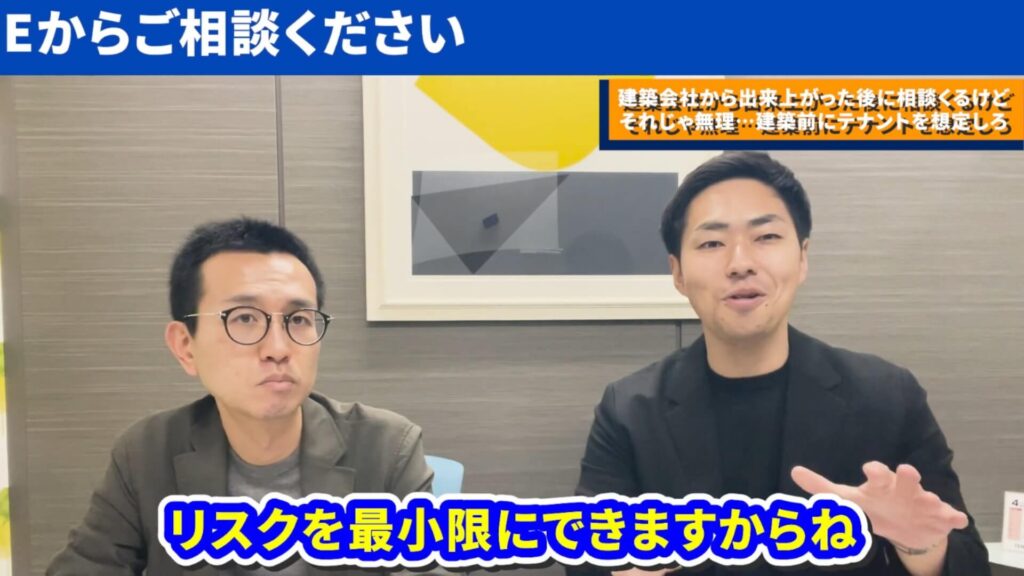
空室リスクを避けるためには、完成後ではなく「建築前の段階で相談する」ことが鍵となります。ここでは、実際の成功事例を通して、建築前から動く重要性と、成果につながる具体的な取り組みを解説します。
建築前の相談が未来を変える!成功事例から学ぶテナント戦略
くっつー:最終的にその相談案件って、どういう流れになったんですか?
やまや:その後、賃料と想定業種の提案を受けて、すぐ「この条件で募集してください」と言ってもらえたんです。ですので、まずは水面下でネットワークを使って紹介を開始しました。
くっつー:あえて表には出さなかったんですね。
やまや:そうですね。まだ建築確認も戻ってきたばかりの段階で、広告は可能だけど、まずは信頼できるテナント候補に限定して提案したほうがリスクも低いので。
くっつー:なるほど。たしかに、早期に動いて決まれば、建物完成と同時にオープンできるって理想ですよね。
やまや:理想です。今は建築中で、完成が8月予定。だから、うまく進めば10月〜11月には開業できます。
くっつー:まさにタイミング勝負ですね。やまやさんみたいに「建物ができる前から動ける体制」があると強いですね。
やまや:そうですね。普通の不動産屋さんだと建物が完成してから動くんですが、私たちは事前に動けるのが強みです。だからこそ、建築前に相談いただければ、賃料の妥当性や業種のマッチングを事前にご提案できます。
くっつー:建てちゃってから「あれ?決まらない」ってなると本当にリスクが大きいですもんね。そういう失敗を防ぐには、やっぱりもっと早くから相談するのが正解ですね。
やまや:はい。理想は着工前、それが難しくても建築中。タイミングとしては今動くのがベストです。

テナント戦略は「完成後に動く」から「建築前に戦略を立てる」時代へと変化しています。建物ができてから募集を始めると、空室リスクや条件不一致が起きやすくなります。逆に、建築段階からテナントを想定し、賃料設定や業種提案をおこなうことで、完成と同時に収益化を図ることができます
この記事から学べる5つのポイント
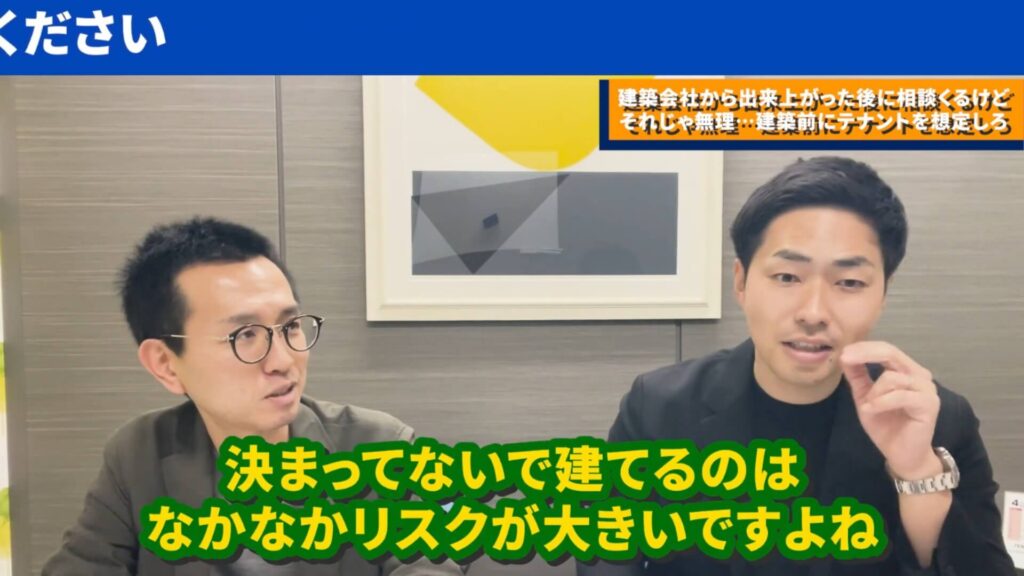
1. 建築中からテナント戦略を始めることで競争力が生まれる
建物完成後に募集を始めるのではなく、建築中からテナント誘致を計画することで、早期成約の可能性が高まります。特に駅近や商業立地では、事前に戦略を練ることで周辺物件との差別化が可能になります。
2. 賃料設定は現場の声とデータをもとに調整する
過去の募集事例や、実際にテナントとのやり取りから得られる「この条件なら検討する」という声を反映することで、空室リスクを最小限に抑えた適正賃料を設定できます。
3. 計画段階から入居者を決めることで安定経営が実現する
建物が完成する前にテナントとの契約を結ぶことで、収益見通しが立ち、事業全体のリスクが大幅に軽減されます。契約時にはペナルティ設定などを含め、確実にオープンまでつなげる工夫も必要です。
4. 賃料設定の見誤りが長期空室を招く
「これくらいで貸せるはず」という感覚的な設定は失敗のもとです。実際に港区でAD12か月をつけても決まらない物件もありました。
正確な市場分析が不可欠です。
5. 建築前の相談が未来の成功を左右する
建物が完成してから動くのではなく、着工前や建築中の段階で戦略を立てることが、収益最大化の近道です。今すぐ動ける体制を整えることが、差別化と成功の鍵になります。
