今回は大阪で開催された店舗開発者交流会に参加してきました。なんと過去最多の450人が集結!そのなかで見えた関西エリア特有の傾向や、私たちが感じた学びをたっぷりお届けします。
この記事でわかること
この記事はこんな方におすすめ
参加者450名!大阪の店舗開発者交流会とは?

今回は東京・福岡での開催を上回る規模感で、全国の出店企業や開発担当者が集まる一大イベントとなりました。まずはその雰囲気と、参加者の属性について詳しくお話ししていきます。
東京・福岡を超える規模感に圧倒!初参加のリアルな感想
くっつー:どうも、テナントの窓口のくっつーです。今回は大阪で開催された店舗開発者交流会に、やまやさんと一緒に参加してきました!
やまや:お疲れさまでした(笑)。今回はほんとすごかったですね。東京で300人くらい、福岡でも150人くらいだったと思うんですけど、今回はなんと450人!
くっつー:過去最高らしいですね。これまで東京・福岡での開催はあったんですけど、今回はとにかく規模がデカい。しかも私たち、今回はじめて2人で参加してきたんですよ。
やまや:大手企業の関西担当の方もいらっしゃいましたが、私の知らない企業も多かったです。でも、名刺交換しながら回ってみると、意外と話しかけやすい雰囲気で良かったですよね。
くっつー:名札の色で業種がわかるのもおもしろかったよね。黒が不動産屋さん、緑がデベロッパーとか。あれで話しかけやすさが一気に変わりました。
やまや:本当に。話しかけるきっかけが自然にできるのって大事ですよね。

今回の交流会は、全国の不動産・デベロッパー・テナント企業など店舗開発に関わる多様なプレイヤーが一堂に会する貴重な場でした。こうしたオフラインの接点こそ、今の時代では逆に希少性が高く、出店意欲のある企業と物件オーナーを結ぶ絶好のチャンスとなります
参加企業の顔ぶれと特徴、関西ならではの傾向とは?
やまや:今回印象的だったのが、東京では出店希望のテナント企業が8〜9割を占めていたのに対し、大阪では7〜8割程度で、関東に比べて施設側・デベロッパーの参加割合が多かったんですよ。
くっつー:そうそう。あとね「関西で出店探してます」って企業がめちゃくちゃ多かった。メールでもあとから連絡いただいて「物件あればぜひ紹介してください」とか。
やまや:やっぱり関東と関西では、ニーズの方向性が全然違うんだなって実感しましたね。
くっつー:知らない企業さんとも多くのことを話せましたよね。ドラッグストアとか飲食とか、あまり東京では聞かない名前の企業も多くて。
やまや:そう、地場で特定のエリアにめちゃくちゃ出店している会社がいたりして。関西独特の動き方をしている企業が多かった印象です。

東京では出店希望のテナント企業が多く、施設側の担当者とのマッチングが課題になることが多い一方で、大阪では商業施設側からの出展誘致が積極的におこなわれている印象です。この違いを理解することで、地域ごとの開発戦略の方向性や、アプローチの方法が変わってきます
地域ごとの出店戦略の違いと新たな気づき

交流会を通して見えてきたのは、地域ごとに出店の進め方や企業の動き方がまったく異なるということ。今回は、ローカルチェーンや地域特化の企業とつながるなかで得られた気づきをご紹介します。
意外と知られていないローカルチェーンの存在感
くっつー:今回、ほんとに関西でしか出してない企業さんがめっちゃ多かったですよね。
やまや:いましたね。しかも、私たちが関東中心に動いているから知らなかっただけで、実は関西では超有名なローカルチェーンだったりして。
くっつー:あと、同じ企業でも、関西の担当者と関東の担当者で全然カラーが違ったりね。
やまや:うんうん。それもすごく新鮮でした。物件への判断の仕方とか、何を重視するかが違っていたりして。
くっつー:たとえば関東の企業は駅前の人どおりを重視することが多いけど、関西の企業は意外と車移動を想定してロードサイドを重視していたりとかね。
やまや:それそれ。だから、全国展開している企業であっても、各地域の出店方針をちゃんと分けているところが多いってことですよね。

同じ企業であっても、地域ごとの担当者によって戦略が異なるケースは珍しくありません。特にローカルチェーンやリージョナルチェーンは、出店エリアに強いこだわりを持ち、地元ならではの情報網や商圏分析をもとに出店を決定しています。このような企業とつながることは、地域特化型の物件を扱う上で大きな強みとなります
首都圏との違いを実感!現場で感じた出店の温度差
くっつー:東京はもう、どっちかというと「出したい」企業のほうが多いから、こっちが営業しなくても向こうから来る感じですよね。
やまや:うん、でも関西は逆で「今ちょうど探しているんですよ」って企業が多くて。すごく能動的に話しかけてきてくれました。
くっつー:実際、交流会のあとに「このエリアでいい物件あったら教えてください」って連絡もけっこう来ましたよね。
やまや:来ました。だから、あの場にいた方たちは本当に出店意欲の高い方ばかりだったっていう印象です。
くっつー:出店を検討している企業と、リアルに今後の物件紹介まで進められる関係が作れるって、すごく貴重なことですよね。

首都圏では供給過多や競争の激化から「出したい企業」が多く、逆に施設側が選ぶ立場にある場合もあります。一方で関西や地方都市では、企業が積極的に物件情報を求めているケースも多く、マッチングがしやすい傾向があります。こうした温度差を理解することは、営業や仲介の戦略において非常に重要です
交流会を通じて広がる人脈と今後の展望

今回の交流会では、ただの名刺交換にとどまらず、実際の出店につながるような“中身のある交流”ができました。ここでは、そのなかで見えてきた今後の展望や、新たな企画構想についてご紹介します。
「テナントの窓口」主催の交流会構想とは?
くっつー:やっぱりこういう場に出てみると「自分たちもやってみたいな」って思っちゃうんですよね。
やまや:わかります。実は前からちょっと構想はあったんですよね。「テナントの窓口」主催の交流会。
くっつー:ですよね。開発担当者さん同士の交流って、最初は意味あるのかなと思っていたけど、話を聞いてみると裏では協力し合っていたりするじゃないですか。
やまや:例えば「あの物件どう思います?」とか「そこの売上どれくらいですか?」って聞き合える関係があると、意思決定が早くなったりするんですよね。
くっつー:そういう場を、うちが作れたら絶対おもしろいし、業界にもプラスになると思うんですよ。
やまや:2026年の目標にしますか?「テナントの窓口主催交流会」開催(笑)。
くっつー:まずは50人くらいからでもいいですよね。東京でやって、そこから全国に広げていけたら。

店舗開発担当者同士のネットワーク構築は、競合を超えて互いに助け合う文化を育てるうえでも大切な取り組みです。非公開情報の共有や、現場ならではの意見交換が可能になることで、より良い出店戦略を練るきっかけにもなります。「テナントの窓口」が中立的な立場で場を提供することで、業界全体の活性化にもつながるでしょう
全国対応への第一歩、ローカルネットワークの重要性
やまや:今って、ネットだけでは出会えない企業さんが多いじゃないですか。特にローカルチェーンとか。
くっつー:それなんですよ。ネットに出てないし、反響もあまり取れない。でもリアルでは動いている企業って多いんです。
やまや:そういう企業と繋がれるのが、こういう交流会の最大のメリットですよね。
くっつー:で、私たち自身が全国をまわってそういう企業と関係を作っていけば「このエリアで物件出ました!」ってときにもすぐ動けるネットワークができる。
やまや:出店先を探している企業と、貸したいオーナーをマッチングする。その架け橋になれるのが「テナントの窓口」の強みだと思うんです。
くっつー:今後は博多、愛知、東京と全国で動いていくつもりです。地域特化の企業とも連携して、より深いネットワークを構築していきたいですね。

ローカルチェーンや地域密着型の出店企業は、ネット上には情報が出てこないことも多く、実際に足を運ばないと接点が生まれにくいのが現状です。そうした企業との直接的な関係構築が、全国対応可能な仲介体制の基盤となります。「テナントの窓口」では地域ごとの特性に応じた提案とマッチングを目指しています
出店企業と物件オーナーをつなぐ架け橋として
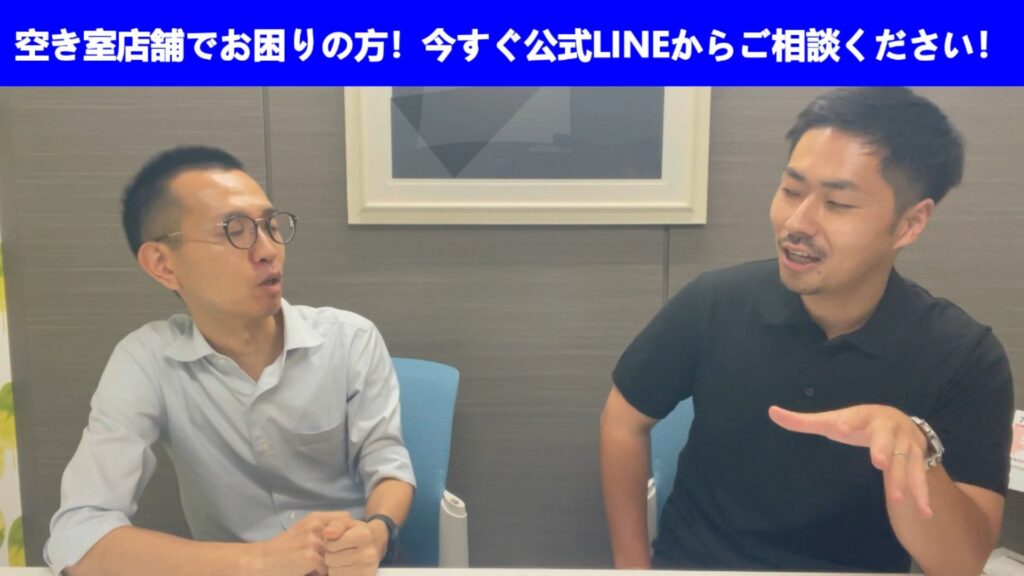
今回の交流会を通して、私たちが強く感じたのは「やっぱりオフラインのつながりが一番強い」ということ。ネットには出てこない、でも出店意欲が高い企業と、物件を貸したいオーナーをどうつなぐか。
ここが私たちの役割であり、今後の大きなミッションだと再確認しました。
オフラインでしか出会えない企業と出会うには
くっつー:やっぱりこういう会に来ている企業って「今出したい」っていう意欲があるところばかりですよね。
やまや:そうなんですよ。逆に「出店止めてます」って会社は来ない(笑)。だから、あの場にいる時点で本気度が高いなって思いました。
くっつー:それに、意外と「この会社出店止めたと思っていた」っていうところが「実はまた動き出している」っていうケースもありましたよね。
やまや:ありました!「ちょうど今また出店フェーズに入ってます」って聞いて「えっ!」ってなった会社が何社かありました。
くっつー:そういう企業さんって、ネット上ではまだ動き出している情報が出てないんですよ。でも、オフの場だと直接話せるから「ここでしか得られない情報」が手に入る。
やまや:それが「テナントの窓口」としての価値ですよね。ネットに頼らず、リアルで関係作っているからこそ、ご紹介できる企業が多くある。

不動産オーナーにとって、出店意欲のある企業と出会えるかどうかは、空室対策の要です。しかしネット掲載だけでは接点が生まれづらく、反響も限られます。だからこそ、こうしたリアルな交流会を通じて、今まさに出店を考えている企業の情報をキャッチし、的確にご紹介できるのが「テナントの窓口」の強みです
出店ニーズのある企業とのマッチングを促進
やまや:私たちがやっているのは、いわば「出したい企業」と「貸したいオーナー」をつなぐ役割ですよね。
くっつー:そう。だから、オーナーさんから「貸したいんだけど、どうやってテナント探せばいいかわからない」って相談を受けたら、まず「どんな企業が合いそうか」から考えるんです。
やまや:で、そのうえで「実際にその企業とつながっているかどうか」が大事。うちはもう、全国のテナント企業と直接やり取りをしているから、そこが強みになってますよね。
くっつー:それも、こういう交流会を通じてリアルなパイプを作ってきたからこそ。実際に顔を合わせているから、企業側も信頼してくれてます。
やまや:それで結果的に、オーナーさんにも早く決まる物件が増えている。これはもう、私たちの活動の成果だなって思います。

物件を貸したいオーナーと、出店を希望する企業の間には、大きな情報のギャップがあります。その橋渡し役として機能するのが「テナントの窓口」です。リアルなネットワークと信頼関係をもとに、的確なマッチングを実現することで、スムーズな出店・成約を可能にします
この記事から学べる5つのポイント

1. 交流会の規模と雰囲気は“参加するだけで価値がある”
過去最大の450名が集まった交流会は、業界関係者同士が一堂に会する貴重な場。名札の色で業種がわかる仕組みや、初対面でも話しかけやすい雰囲気が整っており、名刺交換のハードルも低く、情報交換が非常に活発におこなわれました。
2. 地域ごとに異なる出店ニーズを体感できる
東京では出店希望企業が多く、関西では逆に「物件を探している」施設側の声が目立ちました。地域ごとの出店熱の違いを知ることで、開発戦略の立て方やアプローチ先の優先順位も変わってきます。
3. ローカルチェーンとの接点が“リアル”で生まれる
インターネットに情報が出ていない企業や、ローカルで積極的に出店しているチェーンとのつながりは、現地に行かないと得られません。リアルな出会いが、新しいマッチングの可能性を生み出します。
4. テナント同士の横のつながりが意思決定を加速する
開発担当者同士が交流する場では、競合関係にありながらも、裏で情報共有や協力がおこなわれているケースも多く見られました。こうした関係性は、出店判断やマーケット理解を深める上で非常に有効です。
5. 「テナントの窓口」がつなぐのは“顔の見える信頼関係”
ネットでのマッチングでは伝わらない「温度感」や「タイミング」を、私たちはリアルな現場で感じ取り、全国の物件オーナーと企業をつないでいます。信頼と実績に基づいたマッチングは、今後ますます必要とされるアプローチです。
